これだけは 忘れてはいけない大切なこと
決して忘れないように わたしはそこに鍵をかける
やがてわたしは 鍵をかけたことすら忘れ
あの人の面差しすら 忘れてしまう
* * * * * * * * * *
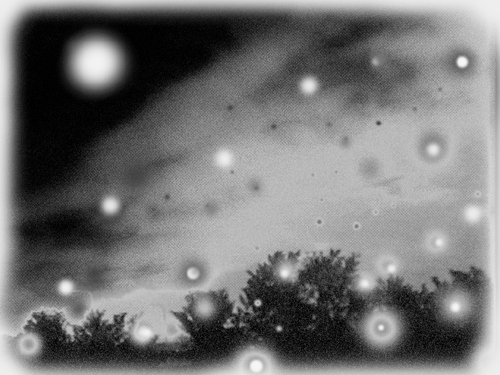 初めに見たものは虚空を舞う幾千もの光だった。
風に乗って舞う綺羅星の粒は、一面を銀世界に染め上げている。雪か何かだと誤解していたが、晩春を思わせる気候と
樹木に息吹く緑の青さが、論理の矛盾を突きつけていた。
落ちてきたその欠片を私は掌で受け止める。
冷たくもなければ、暖かくもない。肌に触れると瞬く間に無に帰した。
「これは何なのだ?」という疑問の答えは出ないまま、広い敷地にポツリと佇んでいた私は小さく息を吹き返して、何度目かの溜息を吐く。
今まで何をしていたのだろうと思い起こそうとして、以前の記憶が綺麗に白紙になっていることに少なからず動揺したのはつい先ほどのことだ。
日時も、場所も、自分の名前さえも忘れた境遇において、唯一分かっているのは『私が女である』というどうでも良いことだけだったというのも
情けない。
身につけている制服からどこかの女学生であり、そしてその私が通っているところが、私の眼前にそびえる洒脱な校舎であることだけは
なんとなく察することができた。
梅雨時を思わせる薄暗い雲の暗幕は、昼とも夕刻ともとれそうで、おおよその時刻を推測することすら叶わないが、早朝や深夜でないこと
だけはたしかな筈だった。
なのに、どうしてあたりはこんなにも静かで、私以外誰一人としていないのだろう。
無音過ぎて耳が痛い。
ここで立っていても意味がないことだけは確かだ。手始めにポケットに手を入れて所持品の確認をする。
何かの手がかりになりそうな物があればと期待したのだが、生徒手帳は元より、記憶に繋がりそうな物は何一つとしてない。
おとなしめの柄のハンカチとポケットティッシュが一つずつ。 財布は持ち歩かないタイプの人間なのか、平日の学校では
充分と思われる小銭が数枚あるだけだ。
現実はこんなものだと肩をすくめると私は一直線に校舎へ向かう。
「おい、誰かいないのか!?」
体育館と思しきアーチ状の建造物を手近の窓から覗いてまわるが、中はガランドウで、ワックスで綺麗に磨かれた床が鈍く光る他は、
これといって目を惹くものはなさそうだ。
そのまま歩を進めると中庭と思しき場所に出た。渡り廊下を挟んで校舎が二つある造りで、こうして間近で見ると意外と大きい。
どちらから探索するか一瞬迷うが、何とはなしに右の棟に足を向ける。
「失礼する」
一階の『職員室』と表札の掛かった部屋はやはり無人だった。
生徒数十人を抱えるであろう担任がここにひとところ集まり、翌日の授業準備や、成績を付けたり、雑務をこなす場にしては異質すぎるほどに
整頓されている。遠慮がちに適当な机の引き出しを開けてみるが中はカラッポだ。そのまま下段の二つも調べてみたが何もない。
書庫棚に整然と詰め込まれたファイルの背表紙は何のラベリングも無く、もしやと思い一冊取り出してパラパラとめくってみた。
「・・・記憶喪失で右往左往している乙女に対して、この冗談はちょっとキツイな」
真っ白のページだけが最後まで続いていた。
次のファイルも、次のファイルも・・・・・・・・・・全部が白紙だった。
窓の外は相変らず光の粒子が淡い燐光を発している。
まるで世界の終わりのように―――
職員室を飛び出し、私は走った。
階段を駆け上がり、二階、三階、四階と顔だけ覗かせたが、廊下に誰もいないことが分かると上を目指す。
屋上に続く階段の終着点にたどり着く頃には、軽く上気してうっすらと汗をかいていたが、私は気にも留めず外へ続くドアに手をかける。
手製で『屋上 立ち入り禁止』と書かれた紙のぶら下がる謹製のドアは重く、ノブを回してみると鍵が掛かっている。
蹴り上げてみるがビクともしない。
舌打ちして周囲を見回すと、目線の少し上に人が一人、何とか潜れそうな窓が見えた。
一瞬躊躇したが、それを蹴破る。破片を取り除き、注意して屋上に降り立つと私は下界を見下ろした。
確かめたいことがあったのだ。
現実ではありえない現実と、体験した不可解な状況。この閉鎖した世界と、私の混乱した思考を打破する何かがあると思ってここに来た。
来たはずなのだ。
それなのに・・・・・・・・
そんなはずはない、あるはずがないと、駄々っ子のように私はイヤイヤと首を振る。
乱れた髪が顔に張り付いて、身体が小さく戦慄いた。
学校の敷地より先の物がことごとく消失している。
校門より先は黒い空間が蠢いており、その中でこの学校だけが孤島のように浮いている。端の方は目を凝らすと、少しずつだが
削れているようだった。ぽろぽろと零れて、闇が世界を侵食していた。
「・・・・・・・・・馬鹿馬鹿しい」
鼻で笑おうとして私の顔は歪んだ。夢か何かだと信じたかったが、汗で張り付いた服の肌触りと、血の気の引いた我が身がどこかで
何かを悟っていた。
光が積もっていく。
どんどん、どんどん。すべてを覆い尽くすように・・・。
緊張した肺に酸素を取り込む行為は予想以上に難航した。自らを叱咤するように一度頬を叩き、挫けそうな気持ちに喝を込める。
異常な事態に巻き込まれている事は理解したが、頭と気持ちが未だ混乱していた。
どこか落ち着ける場所で、気持ちを整理する時間が欲しい。今の私には、この屋上の光景は刺激が強すぎた。
それに・・・・光の粒が私に触れる都度、この学校同様に何かを削られているような喪失感を味わった。
出来れば外に居たくない。
重い足取りで再び校舎に戻る。一時間にも満たない短時間で起った訳の分からない出来事の数々に、私の頭は大分疲れていた。
下りる段数を数える気も起きず、適当な階の適当な教室に入ると、目に付いた机の椅子に腰掛けた。
「さて、どうしたものか」
天上を見上げて私は頭に腕を載せた。独り言を呟いてみたものの、それに対する解はおろか、芥子粒ほどの情報すら仕入れていない私に、
いったいなにが弾き出せるというのだろうかと苦笑する。
いっそこのまま眠ってしまえば、すべてが解決しているのではないかという淡い期待が湧いてしまう。少々気が滅入っているし、
ここで寝てしまうことへの抵抗はさほどない。毛布くらいは欲しいものだがと、あるはずもない物品を求めて教室に視線を彷徨わせて―――
私は腰を浮かせた。
あまりに当たり前すぎて、入った時は気にも留めていなかったが、この教室にはどこか人が時間を過ごした匂いとも言うべき煩雑さが窺えた。
わずかに傾いだ机。生徒が立ち上がって、そのまま在らぬ方向を向いた椅子。消してはいるものの、数式や文章痕の残る黒板と、
その下のチョーク受けに積もった色とりどりの粉粒。ホコリっぽい空気。
後ろの生徒ロッカーに残された物は学業用の書物や、何故か一角を占める筋トレグッズの山、不要と思われる携帯ストラップや漫画、
雑誌、その他諸々。
不思議に思い、席を立ってこの階の教室を一通り見て廻ったが、他の教室は職員室と同じだった。機能的に画一化されて、
人の匂いすらしない無菌室のよう。
再び例の教室に戻った私は背中越しに扉を閉める。
理由は不明だが、この一角だけが例外的な措置を施されていることは確かなようだった。
過剰な期待をすると失望した時の反動が大きいと分かっていても、気持ちはとても正直だ。
高まる鼓動を抑えて、まずは教壇の机にぽんっと無造作に置かれた座席表を手に取った。
見知った名前があれば、そいつのロッカーと机にある物品を物色して、芋蔓式に情報を取得しようという心積もりだったが、
無くなった私の記憶を呼び覚ますような名前はザッと見た限りではなさそうだ。
あの筋トレグッズの所有者が、井ノ原真人という生徒のものである事は了解できたが、無駄な知識を増やしてしまったようで妙に腹立たしい。
能美クドリャフカという生徒にも目が行ったが、単に名前が珍しかったからだろう。
原口雄介、三野瀬仲百合、棗鈴、井上和也、直枝理樹、佐々口洋平、小町洋子、神北小毬・・・・・・・・・・
そうそう巧くいくものではない事は予想していたが、現実の壁というヤツは、ほんの少しも私の期待を叶えてはくれないらしい。
この教室が私と何か関連があると仮定した上での行為も、どうやら無駄に終わったようだ。何人かの机やロッカーを覗き込んだものの、
どれもこれも先ほどのような輝きを失い、私にはただのガラクタの山のようにしか見えない。
疲れた・・・・・・・。
失望は思ったよりも私の気力を萎えさせた。
倦怠感と虚脱感が、私の身体に重く圧し掛かる。
やはりここで寝てしまおうかと思ったが、どうやら私も一端の『女の子』らしい。ベッドと熱いシャワーが恋しかった。
汗でべとついた体と、ごわついた髪を何とかしたいという欲求は、こんな状況においてもしっかりとあるようで、なんだか可笑しくなる。
そういえば、この校舎の正面口玄関に学校の見取り図が掲載されていたことを思い出す。たしか隣の校舎を越えたところに女子寮があった。
そこまで行けばそれらしい設備もあるだろう。
教室を出る前に、ふと気になって座席表を見直した。
無意識に座った座席の生徒に、ほんの少しだが興味があった。
来ヶ谷 唯湖
静謐の湖面を思わせるその名前は、凛として美しいけれど、どこか寂しい。
彼女の私品を物色したが、あまり持ち込むタイプの人間ではないようで、目に付く物はさほどなかった。
気になったのは、鍵の束が放置されていたことと、当人のものと思われる携帯電話が無造作に机の中に置いてあったこと。
メール履歴を盗み見たが、友人と面白おかしくやっていたのだなくらいしか窺えない。後半の履歴の多くは恋文のようだった。
最初の数行は読んでみたものの、他人のプライバシーを侵害している背徳感に私は目を逸らす。
外部に繋がる可能性を期待して、警察と消防署に掛けてみたが不通のようだった。メモリから任意の番号を引き出して掛けてみるが、
・・・・やはり不通である。
待機画面に戻すと、ディスプレイには2007年6月20日の文字。
どうやらそれが今日の日付らしい。
鍵の束の方は、自宅のものと思われるものを含めて全部で3つ。ということは、彼女が自宅に帰る前に突発的な何かが起って、
今のような事象が継続しているのではないかという可能性が想像できたが、それが正しかったとしても今の私には何の解決も提示してはくれない。
「・・・来ヶ谷唯湖女史。キミは私を知っていたのだろうか。知っていたらならば教えて欲しかったな。記憶を失う前の私は、
一体どんな人間だったのかを・・・・」
* * * * * * * * * *
女子寮は新館と旧館があるようだった。
ここもどこか無機質で、人の気配がないのも相変らずだ。
外から見た経年劣化の具合の程は、どちらも似たり寄ったりであまり大差がない。内装は入ってみないことには何とも言えないが、
“学び舎”という大看板を掲げる以上、年頃の女子を満足させるような物は、最低限に留めていると思ってまず間違いないだろう。
共用のシャワー室や、仮眠に使えそうなソファなりを周辺で探してみたものの、どうやら他人の家に上がりこまない限りは、
私の欲求を満たせそうもなかった。
非常事態であることと、記憶も所持品も何もないという身の軽さは、私を大胆にさせた。
数秒後には「家宅侵入が容易そうだ」という単純で物騒な理由から、新館を跨いだ旧館の方へと足を運んでいたが、
どちらを選んでも多分あまり違いはなかっただろう。寮内へは簡単に入ることができたが、個人の部屋のドアは当然のことながら
鍵が施されていたからだ。
仕方がなく裏手に回りこみ、ベランダに降り立った私は、持っていたハンカチを手に巻き、簡易錠のすぐ傍のガラスを叩き割る。
後ろめたさはあったが、今後の生活を考えると、安全かつ快適に過ごせる拠点は咽喉から手が出るほど欲しかった。
礼と謝罪の意味を込めて軽く頭を下げると、ガラスの割れ目に手を差し入れ、開錠して部屋へと入る。
カーテンを退けた先にあったのは・・・カラッポの空き部屋だった。
可愛らしいチェック柄のカーテンだけが、不自然に揺らいでいる。日に焼けた風もなく、住居人がどこかへ引越す際に、
取り残されて間もないのだろうとはじめは思った。
『空クジ』を引いたのだとはじめは失笑してみたけれど、何かがおかしい。
誰も使用していない普通の空き部屋なら、チリの一つくらい堆積してもいいものだが、新築か改装したばかりのマンションのように
床にはチリどころか傷一つない。学生寮という、下から数えた方が早いグレードの物件とは思えない高品質ぶりである。
これと似た違和感はさっき体験した。
校舎での出来事が脳裏を掠め、もしやと思い、二件、三件と同様の手口で犯行を重ねたが、どこも似たようなものだ。
外から見えるカーテン部分だけが取り繕われ、内部がスカスカなところなど、職員室の机や書庫棚のファイルとまるで変わらない。
求めていたふかふかのベッドも無ければ、替えの服を拝借しようとしていた箪笥はおろか、下着一枚見当たらない。
バスルームに向かい、シャワーの水も出ないというトドメを受けて、私は黙って浴槽の縁に腰掛ける。
本当に・・・・・・この世界は何もないんだなとつくづく思い知らされる。
あの教室だけが例外的な空間で、他には何もないハリボテなのだと理解するべきなのだろうか・・・。
右手が痛んだ。開錠する時にガラスで切ったようで、見ると小指の根元から4cmほどパックリ割れていた。
そこから血がとめどなく溢れ出る。スカートに落ちた血は黒く染まり、徐々に大きな沁みを広げていく。
今更到来した痛みに顔をしかめながら、ハンカチで止血して一息つくと、不意に零れそうになった涙を拭う。
ここ居ても仕方がない。多少寝苦しいだろうが、あの教室で寝る他はあるまいと観念した私は、中から玄関の鍵を開けて
のろのろと這い出した。ボロボロになった制服を見つめ、ベッドとシャワーへの未練が捨てきれない私は、出口付近の廊下を
グズグズとしていたが、寮の部屋割り名簿を目にすると、ある可能性に「もしや」と手に取った。
来ヶ谷唯湖 104号室
教室へ戻る事は決意していたが、絶望を抱くか、わずかでも希望を抱いて戻るかでは雲泥の差があった。
来ヶ谷の机にあった鍵束を引っ掴むと、すぐさま女子寮の旧館へと舞い戻り、私は来ヶ谷唯湖の部屋の前に立つ。
鍵の一つを鍵穴に差し入れながら、期待と不安でごちゃ混ぜになった感情が頭の中を駆け巡る。『どうせさっきの部屋と同じだ』
という嘲笑と、『あの教室が例外なら、そのクラスの彼女の部屋にも例外が及んでいる可能性は否定できない』という葛藤が、
カチャリという開錠音で胡散霧消する。
早くなる鼓動と、震える手を制するように深呼吸一つして、私はノブを回す。
開けた先の部屋は・・・簡素ながら、人間の匂いの沁みた落ち着く部屋だった。
蛍光が灯り、水道を捻れば水が出た。ごくごく当たり前のことが得られただけなのに、私の心は浮かれていた。
他人の部屋を使用することに躊躇いはあったが、来ヶ谷唯湖はもとより、人間はもうここには私一人しか居まいという達観があった。
なら有用に使わせてもらうまでだ。
服を脱ぎ捨てると待ち望んだシャワーを浴びて、来ヶ谷唯湖の所有していた服を一揃い拝借する。ジーンズにシャツ一枚という格好だが、
部屋着としてなら文句はない。測ったように丈がピッタリなのは嬉しい誤算である。
軽い家捜しを行ってみたところ、台所の戸棚からはカップメンを含むレトルト系の食料一週間分ほどを見つけることができた。
これで当面は飢餓の心配なさそうだと胸を撫で下ろす。
クローゼットの奥からは救急箱を探し当てた。中を開けてガーゼと包帯を見つけると、ぞんざいに応急処置だけしていた
右手の切り傷に巻いていく。血でぱりぱりに乾いたハンカチをそろりと剥がすと出血したが思ったより傷は浅いようだ。
手を軽く動かしてみる。多少の突っ張り感はあっが、普通に生活する分には問題ない。
ベッドに横になり、ようやくの安楽を堪能すると、枕に顔を埋めながら、私は来ヶ谷唯湖の部屋に視線を転がしていた。
目の前には、暇つぶし用の雑誌が何冊か置いてある。一番新しい表紙にはポップ調に設えられた2007年の7月号というロゴ。
今日が6月20日で、雑誌が7月号だとするなら大体の辻褄は合いそうだと一人納得する。
恐らく来ヶ谷唯湖や多くの人間は6月まではここに居たのだ。日常的な生活をしていたが、何らかの予期せぬ自体が起り、
私だけがここに残されてしまった―――ということなのだろう。
一応の結論は見えても不可解な点は多い。
何故この学校が孤立してしまったのか。そして電気は校舎にも供給されていたが、水道やガスのすべてが備わっているのは
今のところここだけだということ。例外的な空間があの教室と、その教室の生徒であった来ヶ谷唯湖に繋がっているというのなら、
あの教室の生徒を一通り調べてみれば何か分かるかもしれない。
そうすれば、私が誰であるのかというのも自ずと見えてくるのだろうか?
私はここから抜け出すことが出来るのだろうか?
回答を得るまでに私が生きていられるのだろうかという暗雲とした疑問を振り払い、疲労で朦朧とする意識に私は暗幕を下ろした。
今も降り続ける光の欠片―――
それの意味を、私はまだ知らない。
* * * * * * * * * *
初めに見たものは虚空を舞う幾千もの光だった。
風に乗って舞う綺羅星の粒は、一面を銀世界に染め上げている。雪か何かだと誤解していたが、晩春を思わせる気候と
樹木に息吹く緑の青さが、論理の矛盾を突きつけていた。
落ちてきたその欠片を私は掌で受け止める。
冷たくもなければ、暖かくもない。肌に触れると瞬く間に無に帰した。
「これは何なのだ?」という疑問の答えは出ないまま、広い敷地にポツリと佇んでいた私は小さく息を吹き返して、何度目かの溜息を吐く。
今まで何をしていたのだろうと思い起こそうとして、以前の記憶が綺麗に白紙になっていることに少なからず動揺したのはつい先ほどのことだ。
日時も、場所も、自分の名前さえも忘れた境遇において、唯一分かっているのは『私が女である』というどうでも良いことだけだったというのも
情けない。
身につけている制服からどこかの女学生であり、そしてその私が通っているところが、私の眼前にそびえる洒脱な校舎であることだけは
なんとなく察することができた。
梅雨時を思わせる薄暗い雲の暗幕は、昼とも夕刻ともとれそうで、おおよその時刻を推測することすら叶わないが、早朝や深夜でないこと
だけはたしかな筈だった。
なのに、どうしてあたりはこんなにも静かで、私以外誰一人としていないのだろう。
無音過ぎて耳が痛い。
ここで立っていても意味がないことだけは確かだ。手始めにポケットに手を入れて所持品の確認をする。
何かの手がかりになりそうな物があればと期待したのだが、生徒手帳は元より、記憶に繋がりそうな物は何一つとしてない。
おとなしめの柄のハンカチとポケットティッシュが一つずつ。 財布は持ち歩かないタイプの人間なのか、平日の学校では
充分と思われる小銭が数枚あるだけだ。
現実はこんなものだと肩をすくめると私は一直線に校舎へ向かう。
「おい、誰かいないのか!?」
体育館と思しきアーチ状の建造物を手近の窓から覗いてまわるが、中はガランドウで、ワックスで綺麗に磨かれた床が鈍く光る他は、
これといって目を惹くものはなさそうだ。
そのまま歩を進めると中庭と思しき場所に出た。渡り廊下を挟んで校舎が二つある造りで、こうして間近で見ると意外と大きい。
どちらから探索するか一瞬迷うが、何とはなしに右の棟に足を向ける。
「失礼する」
一階の『職員室』と表札の掛かった部屋はやはり無人だった。
生徒数十人を抱えるであろう担任がここにひとところ集まり、翌日の授業準備や、成績を付けたり、雑務をこなす場にしては異質すぎるほどに
整頓されている。遠慮がちに適当な机の引き出しを開けてみるが中はカラッポだ。そのまま下段の二つも調べてみたが何もない。
書庫棚に整然と詰め込まれたファイルの背表紙は何のラベリングも無く、もしやと思い一冊取り出してパラパラとめくってみた。
「・・・記憶喪失で右往左往している乙女に対して、この冗談はちょっとキツイな」
真っ白のページだけが最後まで続いていた。
次のファイルも、次のファイルも・・・・・・・・・・全部が白紙だった。
窓の外は相変らず光の粒子が淡い燐光を発している。
まるで世界の終わりのように―――
職員室を飛び出し、私は走った。
階段を駆け上がり、二階、三階、四階と顔だけ覗かせたが、廊下に誰もいないことが分かると上を目指す。
屋上に続く階段の終着点にたどり着く頃には、軽く上気してうっすらと汗をかいていたが、私は気にも留めず外へ続くドアに手をかける。
手製で『屋上 立ち入り禁止』と書かれた紙のぶら下がる謹製のドアは重く、ノブを回してみると鍵が掛かっている。
蹴り上げてみるがビクともしない。
舌打ちして周囲を見回すと、目線の少し上に人が一人、何とか潜れそうな窓が見えた。
一瞬躊躇したが、それを蹴破る。破片を取り除き、注意して屋上に降り立つと私は下界を見下ろした。
確かめたいことがあったのだ。
現実ではありえない現実と、体験した不可解な状況。この閉鎖した世界と、私の混乱した思考を打破する何かがあると思ってここに来た。
来たはずなのだ。
それなのに・・・・・・・・
そんなはずはない、あるはずがないと、駄々っ子のように私はイヤイヤと首を振る。
乱れた髪が顔に張り付いて、身体が小さく戦慄いた。
学校の敷地より先の物がことごとく消失している。
校門より先は黒い空間が蠢いており、その中でこの学校だけが孤島のように浮いている。端の方は目を凝らすと、少しずつだが
削れているようだった。ぽろぽろと零れて、闇が世界を侵食していた。
「・・・・・・・・・馬鹿馬鹿しい」
鼻で笑おうとして私の顔は歪んだ。夢か何かだと信じたかったが、汗で張り付いた服の肌触りと、血の気の引いた我が身がどこかで
何かを悟っていた。
光が積もっていく。
どんどん、どんどん。すべてを覆い尽くすように・・・。
緊張した肺に酸素を取り込む行為は予想以上に難航した。自らを叱咤するように一度頬を叩き、挫けそうな気持ちに喝を込める。
異常な事態に巻き込まれている事は理解したが、頭と気持ちが未だ混乱していた。
どこか落ち着ける場所で、気持ちを整理する時間が欲しい。今の私には、この屋上の光景は刺激が強すぎた。
それに・・・・光の粒が私に触れる都度、この学校同様に何かを削られているような喪失感を味わった。
出来れば外に居たくない。
重い足取りで再び校舎に戻る。一時間にも満たない短時間で起った訳の分からない出来事の数々に、私の頭は大分疲れていた。
下りる段数を数える気も起きず、適当な階の適当な教室に入ると、目に付いた机の椅子に腰掛けた。
「さて、どうしたものか」
天上を見上げて私は頭に腕を載せた。独り言を呟いてみたものの、それに対する解はおろか、芥子粒ほどの情報すら仕入れていない私に、
いったいなにが弾き出せるというのだろうかと苦笑する。
いっそこのまま眠ってしまえば、すべてが解決しているのではないかという淡い期待が湧いてしまう。少々気が滅入っているし、
ここで寝てしまうことへの抵抗はさほどない。毛布くらいは欲しいものだがと、あるはずもない物品を求めて教室に視線を彷徨わせて―――
私は腰を浮かせた。
あまりに当たり前すぎて、入った時は気にも留めていなかったが、この教室にはどこか人が時間を過ごした匂いとも言うべき煩雑さが窺えた。
わずかに傾いだ机。生徒が立ち上がって、そのまま在らぬ方向を向いた椅子。消してはいるものの、数式や文章痕の残る黒板と、
その下のチョーク受けに積もった色とりどりの粉粒。ホコリっぽい空気。
後ろの生徒ロッカーに残された物は学業用の書物や、何故か一角を占める筋トレグッズの山、不要と思われる携帯ストラップや漫画、
雑誌、その他諸々。
不思議に思い、席を立ってこの階の教室を一通り見て廻ったが、他の教室は職員室と同じだった。機能的に画一化されて、
人の匂いすらしない無菌室のよう。
再び例の教室に戻った私は背中越しに扉を閉める。
理由は不明だが、この一角だけが例外的な措置を施されていることは確かなようだった。
過剰な期待をすると失望した時の反動が大きいと分かっていても、気持ちはとても正直だ。
高まる鼓動を抑えて、まずは教壇の机にぽんっと無造作に置かれた座席表を手に取った。
見知った名前があれば、そいつのロッカーと机にある物品を物色して、芋蔓式に情報を取得しようという心積もりだったが、
無くなった私の記憶を呼び覚ますような名前はザッと見た限りではなさそうだ。
あの筋トレグッズの所有者が、井ノ原真人という生徒のものである事は了解できたが、無駄な知識を増やしてしまったようで妙に腹立たしい。
能美クドリャフカという生徒にも目が行ったが、単に名前が珍しかったからだろう。
原口雄介、三野瀬仲百合、棗鈴、井上和也、直枝理樹、佐々口洋平、小町洋子、神北小毬・・・・・・・・・・
そうそう巧くいくものではない事は予想していたが、現実の壁というヤツは、ほんの少しも私の期待を叶えてはくれないらしい。
この教室が私と何か関連があると仮定した上での行為も、どうやら無駄に終わったようだ。何人かの机やロッカーを覗き込んだものの、
どれもこれも先ほどのような輝きを失い、私にはただのガラクタの山のようにしか見えない。
疲れた・・・・・・・。
失望は思ったよりも私の気力を萎えさせた。
倦怠感と虚脱感が、私の身体に重く圧し掛かる。
やはりここで寝てしまおうかと思ったが、どうやら私も一端の『女の子』らしい。ベッドと熱いシャワーが恋しかった。
汗でべとついた体と、ごわついた髪を何とかしたいという欲求は、こんな状況においてもしっかりとあるようで、なんだか可笑しくなる。
そういえば、この校舎の正面口玄関に学校の見取り図が掲載されていたことを思い出す。たしか隣の校舎を越えたところに女子寮があった。
そこまで行けばそれらしい設備もあるだろう。
教室を出る前に、ふと気になって座席表を見直した。
無意識に座った座席の生徒に、ほんの少しだが興味があった。
来ヶ谷 唯湖
静謐の湖面を思わせるその名前は、凛として美しいけれど、どこか寂しい。
彼女の私品を物色したが、あまり持ち込むタイプの人間ではないようで、目に付く物はさほどなかった。
気になったのは、鍵の束が放置されていたことと、当人のものと思われる携帯電話が無造作に机の中に置いてあったこと。
メール履歴を盗み見たが、友人と面白おかしくやっていたのだなくらいしか窺えない。後半の履歴の多くは恋文のようだった。
最初の数行は読んでみたものの、他人のプライバシーを侵害している背徳感に私は目を逸らす。
外部に繋がる可能性を期待して、警察と消防署に掛けてみたが不通のようだった。メモリから任意の番号を引き出して掛けてみるが、
・・・・やはり不通である。
待機画面に戻すと、ディスプレイには2007年6月20日の文字。
どうやらそれが今日の日付らしい。
鍵の束の方は、自宅のものと思われるものを含めて全部で3つ。ということは、彼女が自宅に帰る前に突発的な何かが起って、
今のような事象が継続しているのではないかという可能性が想像できたが、それが正しかったとしても今の私には何の解決も提示してはくれない。
「・・・来ヶ谷唯湖女史。キミは私を知っていたのだろうか。知っていたらならば教えて欲しかったな。記憶を失う前の私は、
一体どんな人間だったのかを・・・・」
* * * * * * * * * *
女子寮は新館と旧館があるようだった。
ここもどこか無機質で、人の気配がないのも相変らずだ。
外から見た経年劣化の具合の程は、どちらも似たり寄ったりであまり大差がない。内装は入ってみないことには何とも言えないが、
“学び舎”という大看板を掲げる以上、年頃の女子を満足させるような物は、最低限に留めていると思ってまず間違いないだろう。
共用のシャワー室や、仮眠に使えそうなソファなりを周辺で探してみたものの、どうやら他人の家に上がりこまない限りは、
私の欲求を満たせそうもなかった。
非常事態であることと、記憶も所持品も何もないという身の軽さは、私を大胆にさせた。
数秒後には「家宅侵入が容易そうだ」という単純で物騒な理由から、新館を跨いだ旧館の方へと足を運んでいたが、
どちらを選んでも多分あまり違いはなかっただろう。寮内へは簡単に入ることができたが、個人の部屋のドアは当然のことながら
鍵が施されていたからだ。
仕方がなく裏手に回りこみ、ベランダに降り立った私は、持っていたハンカチを手に巻き、簡易錠のすぐ傍のガラスを叩き割る。
後ろめたさはあったが、今後の生活を考えると、安全かつ快適に過ごせる拠点は咽喉から手が出るほど欲しかった。
礼と謝罪の意味を込めて軽く頭を下げると、ガラスの割れ目に手を差し入れ、開錠して部屋へと入る。
カーテンを退けた先にあったのは・・・カラッポの空き部屋だった。
可愛らしいチェック柄のカーテンだけが、不自然に揺らいでいる。日に焼けた風もなく、住居人がどこかへ引越す際に、
取り残されて間もないのだろうとはじめは思った。
『空クジ』を引いたのだとはじめは失笑してみたけれど、何かがおかしい。
誰も使用していない普通の空き部屋なら、チリの一つくらい堆積してもいいものだが、新築か改装したばかりのマンションのように
床にはチリどころか傷一つない。学生寮という、下から数えた方が早いグレードの物件とは思えない高品質ぶりである。
これと似た違和感はさっき体験した。
校舎での出来事が脳裏を掠め、もしやと思い、二件、三件と同様の手口で犯行を重ねたが、どこも似たようなものだ。
外から見えるカーテン部分だけが取り繕われ、内部がスカスカなところなど、職員室の机や書庫棚のファイルとまるで変わらない。
求めていたふかふかのベッドも無ければ、替えの服を拝借しようとしていた箪笥はおろか、下着一枚見当たらない。
バスルームに向かい、シャワーの水も出ないというトドメを受けて、私は黙って浴槽の縁に腰掛ける。
本当に・・・・・・この世界は何もないんだなとつくづく思い知らされる。
あの教室だけが例外的な空間で、他には何もないハリボテなのだと理解するべきなのだろうか・・・。
右手が痛んだ。開錠する時にガラスで切ったようで、見ると小指の根元から4cmほどパックリ割れていた。
そこから血がとめどなく溢れ出る。スカートに落ちた血は黒く染まり、徐々に大きな沁みを広げていく。
今更到来した痛みに顔をしかめながら、ハンカチで止血して一息つくと、不意に零れそうになった涙を拭う。
ここ居ても仕方がない。多少寝苦しいだろうが、あの教室で寝る他はあるまいと観念した私は、中から玄関の鍵を開けて
のろのろと這い出した。ボロボロになった制服を見つめ、ベッドとシャワーへの未練が捨てきれない私は、出口付近の廊下を
グズグズとしていたが、寮の部屋割り名簿を目にすると、ある可能性に「もしや」と手に取った。
来ヶ谷唯湖 104号室
教室へ戻る事は決意していたが、絶望を抱くか、わずかでも希望を抱いて戻るかでは雲泥の差があった。
来ヶ谷の机にあった鍵束を引っ掴むと、すぐさま女子寮の旧館へと舞い戻り、私は来ヶ谷唯湖の部屋の前に立つ。
鍵の一つを鍵穴に差し入れながら、期待と不安でごちゃ混ぜになった感情が頭の中を駆け巡る。『どうせさっきの部屋と同じだ』
という嘲笑と、『あの教室が例外なら、そのクラスの彼女の部屋にも例外が及んでいる可能性は否定できない』という葛藤が、
カチャリという開錠音で胡散霧消する。
早くなる鼓動と、震える手を制するように深呼吸一つして、私はノブを回す。
開けた先の部屋は・・・簡素ながら、人間の匂いの沁みた落ち着く部屋だった。
蛍光が灯り、水道を捻れば水が出た。ごくごく当たり前のことが得られただけなのに、私の心は浮かれていた。
他人の部屋を使用することに躊躇いはあったが、来ヶ谷唯湖はもとより、人間はもうここには私一人しか居まいという達観があった。
なら有用に使わせてもらうまでだ。
服を脱ぎ捨てると待ち望んだシャワーを浴びて、来ヶ谷唯湖の所有していた服を一揃い拝借する。ジーンズにシャツ一枚という格好だが、
部屋着としてなら文句はない。測ったように丈がピッタリなのは嬉しい誤算である。
軽い家捜しを行ってみたところ、台所の戸棚からはカップメンを含むレトルト系の食料一週間分ほどを見つけることができた。
これで当面は飢餓の心配なさそうだと胸を撫で下ろす。
クローゼットの奥からは救急箱を探し当てた。中を開けてガーゼと包帯を見つけると、ぞんざいに応急処置だけしていた
右手の切り傷に巻いていく。血でぱりぱりに乾いたハンカチをそろりと剥がすと出血したが思ったより傷は浅いようだ。
手を軽く動かしてみる。多少の突っ張り感はあっが、普通に生活する分には問題ない。
ベッドに横になり、ようやくの安楽を堪能すると、枕に顔を埋めながら、私は来ヶ谷唯湖の部屋に視線を転がしていた。
目の前には、暇つぶし用の雑誌が何冊か置いてある。一番新しい表紙にはポップ調に設えられた2007年の7月号というロゴ。
今日が6月20日で、雑誌が7月号だとするなら大体の辻褄は合いそうだと一人納得する。
恐らく来ヶ谷唯湖や多くの人間は6月まではここに居たのだ。日常的な生活をしていたが、何らかの予期せぬ自体が起り、
私だけがここに残されてしまった―――ということなのだろう。
一応の結論は見えても不可解な点は多い。
何故この学校が孤立してしまったのか。そして電気は校舎にも供給されていたが、水道やガスのすべてが備わっているのは
今のところここだけだということ。例外的な空間があの教室と、その教室の生徒であった来ヶ谷唯湖に繋がっているというのなら、
あの教室の生徒を一通り調べてみれば何か分かるかもしれない。
そうすれば、私が誰であるのかというのも自ずと見えてくるのだろうか?
私はここから抜け出すことが出来るのだろうか?
回答を得るまでに私が生きていられるのだろうかという暗雲とした疑問を振り払い、疲労で朦朧とする意識に私は暗幕を下ろした。
今も降り続ける光の欠片―――
それの意味を、私はまだ知らない。
* * * * * * * * * *
 それからというもの、来ヶ谷唯湖の寮部屋を拠点に、私の校内の探索は毎日のように行われた。
初めに確認した『来ヶ谷唯湖』という女性徒。彼女の席に隣接する生徒の寮部屋から一つずつ潰していくという
地味な作業からのスタートだったが、目的意識があるだけで孤独という寂しさは何とか紛らわすことができていた。
ベランダのガラスを壊すには、教室にあったダンベルセットの中から、長さ30cmほどの鉄棒を失敬して使わせてもらっている。
鉄棒を振り回して無人の学校を徘徊する少女―――
想像してみるとただの不良少女のようだが、やっている事はその通りなので言い訳も出来ないなと無理に笑う。
まだ半分ほどしか“作業”は進んでいない。今のところ来ヶ谷唯湖と同様に、例外的に人間の匂いが残存している寮部屋は、
神北小毬、西園美魚、棗鈴、能美クドリャフカの4人ということを確認できていたが、来ヶ谷唯湖ほど完全に部屋が残っているところは
一つもなかった。
神北小毬の部屋は、半分以上が虚無の浸食を受けたような惨状だった。あるラインを境にして、いかにも女の子らしい部屋が
飾り立てられているのに、片側は空き部屋のような有様。西園の部屋は表層の作りはちゃんとしているのに、机や本棚を漁ると
職員室と同じでカラッポか、白紙の束を束ねた装丁の小説が並んでいた。
能美や棗鈴の部屋も似たようなものだ。
進捗は斯様に足踏み状態を維持したままだが、幸か不幸か、この作業の最中、私は“ジョーカー”を拾っていた。
ババ抜きの『ハズレ』か、ポーカーで力を発揮する『当たり』かはまだ見当が付かないが、何らかのヒントを提示している事は確かだった。
来ヶ谷唯湖を含めた例の四人が、同じ写真を所有していたのだ。
多分、それぞれが最も大切に保管できる場所、見栄えの良い最良の場所を選ぶように、あるものは仕舞われ、あるものは飾られていた。
何かの記念なのか、10人の男女が和気藹々と写っている。裏には『リトルバスターズ』と記載され、部活か何かのメンバーで
あることは容易に想像できた。
写真には私も映っていた。
巨漢の男と、いかにも清楚な印象の女性に上下を挟まれる形で、可愛らしく顔だけを覗かせて微笑んでいる。
まともな写真はこの世界ではそれ一枚きり。アルバムを時には見かけることもあったが、収められた写真のすべてが真っ白の紙切れと
化していた。何故かは分からないが、『何か』がこの写真にある―――ということを如実に物語っている。
彼らがどんな連中なのかはこの写真だけでは察することができないが、少なくとも私は幸せだったのだろう。
こんな表情で笑い合える友人が居たのかと思うと、我が事ながら羨ましいと今の自分を省みて、つくづく思い知らされる。
一日の終わりになると、私は毛布に包まりながら、来ヶ谷の寮にあるその写真を眺めては物思いに耽るようになっていた。
どれかは分からないが、多分この中に来ヶ谷唯湖も居るはずだった。
それはつまり、来ヶ谷唯湖と私は面識があったということになる。
私達は、一体どんな話をしたのだろう・・・?
* * * * * * * * * *
何日かが経過した。
昨日、女子寮を一通り終えることができた私は、その日ようやく男子寮に手を付けていた。
座席表の男女を調べる程度なら二、三日で事足りるだろうと当初は楽観していたが、物事には常に山あり谷ありだと、
私は改めて思い知らされる。
全員が地上階であれば苦労などしないのだが、それが上階となると話は別だ。基本的に鍵の掛かった寮部屋への侵入は、
ベランダをつたって二階、三階へよじ登るという行程が必要となる。右手の傷が癒えてない私にとって、この作業はかなり堪えた。
当然、正攻法で正面突破を試みたこともあったが、力任せの破壊や、針金を曲げての鍵の開錠など、体力と時間の浪費だと早々に
悟って以来、専ら壁登りが主流である。
寮部屋がカラッポであれば一瞥して戻れば良いだけの話だが、部屋の内装が保存されていた場合、一通り調べるという作業が
これに加算される。このときほど人の所有する物品の多さに嫌気がさすことはない。一部屋だけで長いときでは半日以上を費やすのだから、
調査は女子寮だけで相当の日数を消費していた。
今回の男子寮の探索で、調べていた生徒が初回から三階であると知ったときの私の気分が如何ほどであったかは推して知るべし―――。
後に回そうかとも思ったが、どうせ、いつかはやらなければならないノルマである。やるなら早めの方がいいと覚悟を決めて、
三階に住居を構える他の二名の部屋も、まとめて片付けたのが数分前のことだ。
先日失敬した水筒から、水が咽喉を伝うのも構わずごくごくと飲み干して、私は息を吐く。作業時には当たり前となって久しい
ジャージの袖で汗を拭うと、大した収穫もなく無駄骨に終わったことを、勤めて忘れてしまおうと次の作業に取り掛かった。
手際は慣れたものだ。傍に置いたバッグから寮の玄関口に張られていた部屋割り名簿と、教室にあった座席表を見比べては、
先ほどの部屋の留意点を書き込んでいく。
その姿は一介の女学生とは思えないほど凛々しいけれど、肌に載った疲労の色は隠しようがない。
孤島に一人だけ取り残された人間がはじめに飢えるのは、人との触れ合いだといわれている。寮部屋を探索する目的が、
その意味合いを変化させつつあるのもそこに原因があるのだろう。例の教室と、生徒たちの関連を解き明かすことよりも、
誰か他に人が居ないかを主眼に寮部屋を放浪している自分に気付いたのは、つい最近のことだ。
記憶喪失による精神的な不安と、「私は誰であるか」という強迫観念。
閉塞した世界と支えのない孤独感が、その気持ちを更に助長していたのだろうが、焦燥は強くなるというのに得られる成果は微々たるものだ。
ベランダをつたって上り下りする私の寮の探索と比べ、日常そのものは平坦で起伏がない。同じ日を何度も繰り返しているような、
奇妙な既知感に囚われてしまう。
そのためか、私がこんな目に合って、いったい幾日経過したのか・・・実を言うと、もうほとんど憶えていない。
降り注ぐ光のカケラは止む事を知らず、同じ風景と、同じ日常の繰り返しに、当の昔に私の心根は折れていたのかもしれない。
感情の限り叫んで、人を求めたこともあった。
「何でこんな目に・・・」と、一日中来ヶ谷唯湖の部屋から出なかったこともある。
私はもう知っている。ここには本当に、私一人しかいないという事を。
けれども、人を探さずにはいられない。暇を見つけては校舎の中も探してはいたが、確率的に誰かが居るとしたら寮部屋以外に
考えられなかった。
不毛と知っていながら、こんなことを続けている私は馬鹿なのだろうか。
それとも、どこかで狂ってしまったのだろうか。
窓を壊しても、部屋をめちゃめちゃに荒らしても、何事もなかったかように翌日にはすべてが元に戻っている事象を目撃してからと
いうもの、どこかで私の心のバランスは崩れ始めていた。
負担ばかりかけていた左腕は小刻みに震えていた。
それが伝染して、震えが身体を覆っていく。
誰でも良い。
ただ・・・誰かと逢って話しをしたかった。
バラバラに壊れそうな部品を繋ぎ止めている私の糸は、今にも切れてしまいそうだ。
それでも平静を装い、次の目標となる男子生徒の部屋を探していたところ、ある名前で目が止まる。
棗恭介・皆川早瀬 312号室
どこかで見たことのある名前だった。
私は最近の記憶を掘り起こそうと、感傷的になっていた気持ちを切り替える。
棗恭介・・・・。棗―――そう、棗鈴だ。
珍しい苗字からも、棗鈴と血が繋がっていると推測するのもあながち的外れではあるまい。調べてみても損はないと判断した私は、
とりあえずの目標を見つけることができて、ほんの少しだけいつもの平静さを取り戻す。
こういう収穫のあるときはいい。思考を循環させている間だけ、嫌なことから目を背けていられるから。
それにしても、例の教室の生徒にしか目が廻っていなかった自分が憎らしかった。
部屋番号からして三階だろう。軽く眩暈を覚えるが、そこはグッと堪えて名簿をバッグに仕舞い、小脇に抱えると、一応、
部屋のドアが開いていないかを調べに階段を上って三階へ向かう。
一度として開錠された状態の寮部屋というものを拝んだ事はないのだが、ベランダをよじ登るという重労働を回避する可能性が少しでも
あるのだ。この階段を上る程度の労力で済むのなら、確認してみる価値はある。
疲弊した身体に鞭打ちながら、私は一段、また一段と足を運ぶ。
それにしても、男子寮の名簿は見ていたのだが・・・棗恭介を見過ごしていたことが、どこか腑に落ちなかった。まぁ、棗鈴の
『家宅捜査』を行うまでは、あまり気にも留めていなかった苗字なのだから、見過ごしていたのも当然といえば当然なのかもしれないが・・・・。
例の写真には確かに兄妹らしい二人の姿が写っていたと思う。いかにもやんちゃそうな男と、どこか困った表情のポニーテールの少女。
棗鈴と棗恭介があの二人だとするなら、私と能美クドリャフカの合わせた四人が、あの写真の中で顔と名前が一致したことになる。
女生徒の来ヶ谷唯湖、神北小毬、西園美魚で女子の数は合うから、残った男子生徒3人を見つけることが今後の課題であろう。
これがすべて終わった先にある予感を、私は勤めて見ないようにしていた。これだけの時間と労力を費やしていながら、得られたものは
友人と思われる9人の存在を映した写真一枚きり。すべてが徒労に終わるであろうことをどこかで悟っていても、止めることなど私に
できるはずもない。
そこで足を留めてしまったら、私は『現実』を見つめなければいけなくなる。
過酷な現実を目の前にすれば、私の心はきっと死んでしまう。
だから私は、あの写真に依存する。
一日の終わりになると、あの中の生徒達との日常を空想しては、現実から飛翔して、もう二度とこの世界へ舞い降りてこないようにと
切に願って布団を被る。漂流したこの世界の方が間違いで、きっと夢か何なのだと自分に言い聞かせて・・・・。
どんなに強くあろうとしたって、私はちっぽけな一人の少女でしかない。力が強かろうが、どんなに賢かろうが、ひとりきりの自分を
満たす糧にはなりはしない。
こんな現実と今こうして付き合っているのだ。
少しくらい夢を見たっていいじゃないか・・・
舞い落ちる光の粒子は、とうとう寮の内部にも浸水していた。
どこから落ちてくるのか、ひらひら、ひらひらと私の目先を過ぎっては、小さな夢を灯しては消えていく。
空ろに沈む私の瞳は、やがてカケラの残骸に吸い寄せられる。
リトルバスターズの面子と、私の間にあった関係はどのようなものだったのだろうかと想いを馳せていると、うつらうつらと舟を漕ぐように、
気付けば私の意識はどこか遠くに流されていた。
私を苛めていた孤独と疲労が、とうとうピークに達してしまったのかもしれない。「こうであったら良いな」という過去を妄想しては、
現実から目を背けようとする何かが、私の『何か』を断ち切ろうと首に手をかけていた。
私が笑っている夢
私がささやかな恋している夢
私が多くの仲間たちに囲まれて、日常の学校生活を過ごす夢
とても甘くて、魅惑的な夢だ。いつまでも続けばいい。あの写真の仲間達に囲まれて、どこまでもどこまでも、楽しく平穏な世界を
ぐるぐると、ぐるぐると・・・・・・・・。
死ぬまで妄想の世界で生き続けれると言うのなら、それは確かに幸せなことなのかもしれない。
ふうっと訪れる陶酔に身を委ね、静かに闇に落ちそうになる私の背中を、誰かがそっと抱きしめたような気がした。
―――そんな世界、僕は認めない・・・・!!―――
誰だったろう?
以前誰かに言われた言葉が木霊した。
華奢な体つきをしているくせに、人一倍健気で、誰よりも優しくて、強い人。
だから私は・・・。
私は・・・・・・・
「・・・どうしたのだろう・・・?」
数日に渡る強行軍で、肉体的にも精神的にも限界に達していたのだろう。階段の途中で崩れるように倒れていた私は、
夢心地の頭を振って起き上がる。
何かを思い出しかけていたような気がしたが、それももう、夢と共に曖昧なものとなっていた。
無理な体勢で倒れていた為か、節々が痛い。散らばった所持品を拾い集め、廊下の窓から外を見回すと、いつの間にか三階まで
来ていたようだ。夢遊病者じみたあんな状態で、よくここまで来たものだと呆れてしまう。
ふと横を見れば314号室は目と鼻の先だ。
この部屋にもやはりあの写真があるのだろうか・・・・。
錠が掛かっていることを覚悟して軽くノブをひねると、拍子抜けるほど簡単にドアが開く。息を呑み、私はゆっくりと中を窺った。
光の届かない深海のように、深い闇が部屋を支配していた。
目を凝らすと、うっすらとだが二段ベッドらしき輪郭や、勉強机、平積みされた数冊の雑誌が識別できる例外的な空間だ。
どうやら棗鈴の血縁者という仮定もあながち間違いではなさそうだ。
例外者の中では私が見つけた初の異性でもある。新たな発見があるかもしれないと期待に胸を膨らませるが、こう暗くては
作業に差し支えが出る。
手始めに遮光カーテンをなんとかしないと・・・
部屋に足を踏み入れた私のすぐ後ろで突如ドアが閉まった。
慌ててドアを振り返るが暗くて何も見えない。おおよその見当で延ばした私の腕は虚空を薙いだ。
「・・・・・来ヶ谷・・・か?・・・どうやってここに?」
男の声が響いた。
人間の声だ。
記憶を失った私にとっては、“生まれて初めて聞く”他人の声。
一人じゃないことの嬉しさが全身を駆け巡るが、男の言葉を反芻していくうちに、私はゆっくりとだが醒めていく感覚を憶えた。
繋がった先の『ソレ』と自分を照らし合わせて、何かが鮮明になっていく。記憶の奔流と、混濁した感情。
頭の中が割れそうに痛むのを堪えて、確定した私という個体の正式名称を口にする。
「私が・・・・・・・・・・来ヶ谷・・・唯湖なのか・・・・・・・・・」
じゃあ、例の教室で無意識に自分の机に座ったことは一つの必然だったのか?
鍵と携帯が放置されていたのは、記憶喪失前の私が置いていただけ?
じゃあ、あの例外的な空間は・・・・
嵌り続けるピースの数は膨大に膨れ上がる。
圧倒的な物量に堪えきれず膝を突き、それでも私は男の顔を見ようと闇に目を凝らす。
「お前は誰だ・・・・・棗恭介か?」
質問の意味を巧く把握できなかったのだろう。
しばらくの沈黙が終わると、男は意外そうな声を上げた。
「・・・・おいおい、まさか完全に記憶をなくしているのか? そんな状態でどうやってあの世界を持続させて―――いや、そうか・・・。
それで俺の部屋に繋がったというわけか。記憶喪失にでもならなければ、お前が好き好んで俺の部屋にくるはずもないし・・・・
整合性は確かに取れるが・・・・」
「・・・・・・何が言いたい!? なにを言っている!?」
一人納得する男に苛立ちを隠せない私は、奥へと進む。
部屋の隅に浮かぶシルエットが、もぞりと動いた。
「来ヶ谷。お前の世界はもう終わりを迎えている。そこにあるのはただの『残骸』だ。“こっち”と繋がったのは、綻びの隙間を
巧く掻い潜れたからだろうという仮定しか出来ないが・・・・恐らく、お前の世界が完全に終わりを迎える前兆だろう。
・・・今のお前に話しても理解できないだろうが、お前の願いにはそもそも無理があったんだよ。『永遠』を願ったところで
破綻が生じる事は分かっていたはずなのに・・・・どうしてお前はその世界を願ってしまったんだ・・・」
分からない。
彼が何を言わんとしているのか私には理解できない。
「他に、願うべきものがあっ・・・た・・・ろ・・・。両親・・・関係・・・の修・・・・・・・・・・の・・・・に・・・」
「待ってくれ! 聞こえない! この世界はまやかしなのか? どうすればここから出られる!?」
男の声が遠い。物理的距離は3mもないというのに、歩み寄る私と男との距離はいくら経っても縮まらなかった。
あと、少し・・・あと少しがもどかしい。
「・・・・な・・・おえ・・・・き・・・。・・・わ・・・す・・・・れ・・・」
手の先が男に届いたのは直後のことだ。布地と思し手触りを頼りに私は一気に男を引き寄せる。
聞きたい事は山ほどある。そして男はそれを答えれるだけの知識を持ち合わせているらしかった。まずは顔だ。
写真の男なら、リトルバスターズについても聞けるだろうしこちらとしては好都合だ。
私はカーテンを力任せに引き毟る。レールごと盛大に剥がれて、外光が闇を駆逐する。
そうして目の前にあったのは、襤褸と化した唯の布切れだ。
男はおろか、部屋の中に確かにあったはずの二段ベッドもなければ、男のもとへ向かう最中によけたはずの、ゴミや雑誌の山は
陰も形もなくなっている。
狐に抓まれた面持ちの私は、辺りを見回して更に呆然とする。
314号室だった部屋は廃墟と化していた。
天上や側壁は失われ、吹きさらしの空からは、光の飛礫が舞い込んでいた。
いや、314号室だけじゃない。隣も、その隣も・・・・男子寮はおろか、数十メートル先にある校舎、女子寮、体育館。
何から何までが廃墟一歩手前の零落ぶりを晒している。
この世界の終わりの前兆―――
男は確かにそういっていた。
それが・・・・これか?
漂流していた学校の敷地はとうとう闇に飲まれ、グランドの半分近くが削れてなくなっている。侵食速度は以前と比べ物にならないほど
速く、数時間もすれば、すべてがあの闇に覆われるだろう。ここでオメオメしてたら私も崩壊に巻き込まれる。
314号室前に転がっていたバッグを抱えて、私は寮部屋を後にした。
とにかくこの世界から抜け出す方法を探さなければいけない。
最後に男はなんと言った?
なお・・え・・・・・直枝・・・・・
どこかでそんな名前を見かけたような気がして、座席表と、寮の部屋割り表を私は取り出した。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なんだ・・・・・・これは・・・・?」
プリンターで印刷された紙面の文字は、数十年の時を経たように擦れていた。名前を確認しようにも、うっすらと見えるのは
罫線くらいのもの。私の座席の場所がどうにか判断できる程度の解像度で、誰かの名前を特定するなどできるはずもない。
ついさっきまで普通の紙であったものが、どうやったらこうまで劣化するというのだ。
せっかく、何かが見えはじめたというのに・・・・!
私は力任せに地面に叩きつける。その一撃が紙書類の寿命を終わらせた。
チリ屑と化した紙吹雪は上空を舞い、それは突然、光の粒子となって虚空へと還っていく。
唖然とする光景を目の当たりにして、私はようやく光のカケラの正体に気付くことができた。地面も、草木も、建物に至るまで・・・・。
降っていたと思っていた光の粒子は、この世界を構築していた物質そのものなのか。
作り物の世界。その残骸の中で彷徨っていたのがこの私・・・来ヶ谷唯湖だったと言うわけだ。じゃあ私も誰かに創造にされた
作り物なのだろうか?
可能な範囲で自分の身体を調べてみるが、光の粒子が私から漏れ出す気配はない。少しだけ安堵するが、状況は何も変わってなどいない。
何か・・・何かできることはないかと思考を巡らせる。
直枝という人物の手がかりは何もないといっていいが、ある程度の推測は可能だ。リトルバスターズのメンバーの一人とするならば、
あの教室のどこかにそいつの机があるかもしれない。運がよければ所持品を見つけ・・・・そして更に運がよければそこから脱出する
手段―――。
常識的に考えて、そんなご都合的な可能性はゼロだとは分かっている。
けれど、動かなければここで屍を曝すだけだと走り出す。
例の教室はまだ健在だった。隣接する教室が既に朽ちているというのに、ここだけ日常の息吹を保管している。
区切られた境界を潜るように、私は教室の中へと舞い戻っていた。
窓の外から見える世界の終わりを告げる光は、その数を何千、何万と増やして一面を真っ白に塗り潰している。
チラホラとその光に混じって、遠い彼方の風景が二重写しに霞んでいた。
季節は初夏だろうか。
暑い日ざしが差し込み、木々がその緑を深めている。
白く塗られたキャンパスの先には、私の見知らぬ世界があった。
この世界はもう崩れ始めているのだ。このままここで息を潜めていれば、もと居た場所へと帰ることができるのかもしれないという
誘惑が過ぎるが、私は大きく首を振る。
違う。
まだ帰れない。帰ってはいけないと本能が警告していた。
私は何かを忘れている。この世界に何かを置き忘れたままだ。
戻った瞬間それは消えてしまう。
それではダメ。
それではこの世界を願った・・・・・・・意味が・・・・
今・・・私は何を口走った?
あの男と出会ったことで、何かが・・・・忘れていた記憶の断片が、ここに来て私の中に生まれつつあるのだろうか。
かつては他人だと思っていた来ヶ谷唯湖。その席に私は座り、必死に何かを思い出そうと努力する。そう、私は何かを願ったのだ。
全てをかなぐり捨ててそれだけを願った。それだけあれば他はもういらないとさえ祈った自分の気持ち・・・・。
あったはずなのに・・・・
痛いくらいに拳を握る。
思い出せないことが自分の罪であるかのように髪をぐしゃぐしゃにすると、声にならない絶叫を上げて私は机を蹴り飛ばした。
愚か過ぎる。
願いをした本人が全てを忘れているというのに、その願いだけが一人歩きをして、こんな世界を未だに残し続けているという事実が。
この世界は、私に何かを教えようとしている。そうでなければ、こんなにも無残になった状態で存続し続ける意味がない。
それとも無意識に、私という主体がこの世界に今に至るまで何かを願い続けているのかどちらだろう。
ダメだ・・・考えても分からない。
力なくうな垂れる私の顔はとうとう下を向いた。
携帯電話があった。
来ヶ谷唯湖の・・・私の携帯電話が、机が蹴り飛ばされた拍子に転がっていた。
全身に鳥肌が立つ。
藁をも掴むように私はそれを手に取った。
そうだ。あったはずだ。メールで、私は誰かに宛てて恋文を送り続けていた。
確信する。私が思い出すべき事はそれ以外にありえない、と。
私はゆっくりとメール履歴のボタンを押した。
受信メールはありません
たった一文の報告に、私の思考は停止した。
そして、ただ可笑しくて笑い出す。
そんな馬鹿な。あるはずがない、何かの間違いだともう一度、履歴ボタンを押す。
受信メールはありません
・・・・・・ありえない。
ありえない。ありえない。ありえない。
消した記憶はない。机から落ちた程度でメモリが飛ぶとも思えない。
送信メールの履歴も調べてみるが、こちらもどういうわけか『送信メールはありません』という無機質な文面が羅列されている。
電話の着信履歴、リダイヤル、友人のメールアドレスや電話番号の全てが初期化されていた。
購入したての市販品のようなものに成り下がってしまったそれを取り落とし、ただ無言で私は首を振る。最後の希望が枯れ落ちてしまった。
それを合図に、守られていた教室、机、私品の多くから・・・・光が洪水となってあふれ出す。
手遅れだったのだというには、あまりにも『それ』は近くを通り過ぎていた。
私が・・・来ヶ谷唯湖が思い出すべきだった何かを連れて、世界は徐々に白に埋もれていく。
こんなことで終わるのか?
この程度で私は何かを失ってしまうのか?
いやだ、いやだ・・・・!
気力を揺り起こして立ち上がると、もう不要とは分かっていたが、何かを閉じ込めていた携帯を、“遺品”を手に取るように
大事に抱えて私は教室を抜けた。ドアを抜けると同時に、他の教室と同様の姿に聖域は崩れ落ち、置いてあった私のバッグも、
それの余波を受けて光となって消えた。
よろよろと立ち上がる私の手元に残ったのは携帯と、三つの鍵束。
記憶を保持していた頃の、来ヶ谷唯湖の遺留品とも言うべきそれが、私に与えられた唯一の活路だった。
鍵の一つは寮の部屋としても、残りの二つは私に何を示唆しているのだろう。
一つは寮の鍵と似た形状で、残りの一つは3cmほどの長さのチャチな造りをしている。
使用場所は皆目見当も付かないが、何かの役に立つかもしれない。ポケットに仕舞うと、渡り廊下を抜けて、私は対向側の校舎へと
移動する。闇の侵食は、程なく向かいの校舎を飲み込んだ。気付けば寮側に立っていたこの校舎しか残っていない。
廃校同然のここが、最後の砦というわけだ。
だが、まだ全てが終わったわけじゃないと私は自らを鼓舞する。
崩壊が始まって、全てのものが崩れ落ちているという事は、逆に考えればチャンスでもある。
寮や例の教室のある校舎は一通りの調査を行ったが、寮側にある校舎は優先順位が低かったこともあり、それほど調べたわけではないのだ。
仮にあの教室のように、例外的な空間が存在するのであれば、今のこの状況なら、記憶を喪失した私にでも重要性が視覚的に
把握することができる。要は崩壊していない場所や物を探せばいい。
見つけるのだ。この崩壊の跋扈した世界で、来ヶ谷唯湖の想いを保持した『何か』を。
今の今になって、ようやく私は疑問の氷解音を聞いていた。
答えは単純だったのだ。
この世界の影響を受けずに残存していた例外的な空間や物は、私と繋がっていた。
リトルバスターズの写真
その中で笑う友人達の部屋
私が通っていた教室
来ヶ谷唯湖である私の部屋
全部、全部意味があった。
無意味なものなんて一つもなかったのだ。
ガラクタと吐き捨てた、あの教室にあった物品も突き詰めていれば、きっと何かの役に立ったかもしれないのに。
一階の廊下をひた走っていた私は『それ』を見つけていた。
周囲と比較して充分綺麗なドア。影響を受けていない証拠だ。
「放送室」というネームが貼られているが、果たしてこんな場所に何かあるのだろうかと首を傾げてしまう。しかも、当然のように
施錠されたドアはビクともせず、崩壊を起していない代わりに、私をも締め出して盤石の鉄壁を誇っていた。
裏から何とかならないかと外に向かおうとしたが、玄関口で生じた鈍い音が、私の勇み足を押し留める。ぐらりと校舎が揺れたのは
その直後だ。
玄関左手の校舎下の地表がとうとう闇に食われたのだ。寄りかかる土台を失くした校舎は自重に負けて半壊した。
体勢を低くしていた私には幸いにも大した怪我はなかったが、振動でもんどりを打った拍子に足首を挫いていた。
震災の第一波が収まるのを確認して、ひょこひょこと足を引き摺りながら窓に向かうと、私は身を乗り出して外を窺う。
あたり一面は闇の海と化していた。
空には崩れ落ちた天蓋がぽっかりと開いている。それはもう空というよりも、きらきらと光る豪華なシャンデリアを叩き壊した
瞬間の映像だ。ぶちまけられた光の粒が闇の黒に映えて、思わず見惚れてしまうそうだ。
天も地も周囲の建造物も根こそぎ消滅している。
食べ残しはここだけというわけだ。
あまり考える時間もないというのに、この堅牢なドアを攻略する方法で、ろくな案が浮かばない。寮のベランダから侵入というような
アクロバットな小技はやりたくても、右手は痛むし、足首は痛い慢心創痍状態。
移動も無理、力技も無理ときてはさすがの私も手の打ちようがない。
「もうここまでかな・・・・」
ニヒルなタフガイなら、ここでタバコの一つでも燻らせるのだろうが、生憎と私の手元に、そんな物は・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
サイドポケットに手をやると金属特有の硬質な手触りがあった。
取り出してみると鍵の束。
一つは寮の鍵。
そして一つは同系の鍵。
まさかな、とは思いつつも、その鍵を錠に差し込むと見事に嵌り込む。
そのまま半時計方向に回すとカチリ―――という小気味いい音を立てて部屋は私を招きいれていた。
狭い部屋だ。
もともと放送だけを目的としているであろう部屋に、マイクやら面倒そうな設備がこれでもかと突っ込まれているのだから無理もない。
奥には電子ピアノらしきデカブツが鎮座しておりなかなかに壮観だ。
放送室に入ると同時、朝からずっと酷使し続けた身体はもう限界だった。倒れこむようにフローリングの床に身体を横たえると、
私はそのまま身動き一つ取れなくなる。
床の冷たさがほてった身体に心地いい。妙な達成感を憶えて、私はこの世界で初めて作り笑いじゃない、本当の微笑いを浮かべることが
できた。
ここが私の終着点。
そして、多分・・・記憶喪失以前の来ヶ谷唯湖が一番の想いを込めた場所。
記憶喪失以前の私がここに何を感じ、何を経験して、何をしていたのかは分からない。
分からないけれど、それはきっととても大切なことだったんだろう。
闇と光のカケラに飲みこまれもせずに、最後までここが残ったのも偶然じゃない。
“ここを中心にして作られた世界”だからこそ、最後に残ったのがここだったというだけなのだと思う。
それが分かっただけでも、私は満足だった。
胸に酸素を充填すると、やがて私は大きく息をつく。
一人の少女によって創られた世界は、とうとうその限界を迎えていた。
不完全で、不恰好だったカタチは歪み、『世界の中心』である放送室へと闇は進行する。
壁が光のカケラとなって消えていく。
床も、機材も、そして、私自身も・・・・
恐くはなかった。
徐々に埋没する足はその存在感を失い、やがて腿、腰、胸を覆い・・・
最後に私の顔はとぷりと沈んだ。
結局、直枝という人物だけがよく分からなかったなと、私は感慨深く呟いた。
男なのだろうとは薄々とは感じていたが、やはりそれが誰なのかを理解することができないまま、来ヶ谷唯湖である『私』が、
私ではなくなることが少しだけ心残りといえた。
混濁した意識の中で、私は奇妙な夢を見る。
私が誰かに恋をしているという夢。
それは叶わぬ恋であり、私自身も分かっている悲しい夢。
とても儚く悲しいけれど、分かっていても、やはり私は彼を好きになるしかなかったんだと諦めたように小さく頬笑う。
けれどそれは夢。
どんなに苦しくて、恋しくても、それは夢。
だから忘れてしまおう。
悲しかったことも嬉しかったことも、全部この夢に詰め込んで―――
あとがき
|ω・`)
うん、多分一番空気読めてない作品だと思います。
というわけでまずは一言言わせてください。
スンマセンでしたー!!!!!!orz
さて(ぉ
今回のSSは、ウチのブログの『二次創作考察小説』というSSの番外編的位置付けの作品だったりします。やれることなら来ヶ谷の
補完的な作品もやりたいなと思っていた自分にとって今回の来ヶ谷祭はまさに渡りに船ということで投稿させていただきましたm(_ _)m
基盤にあったのは来ヶ谷シナリオの終盤からラストへの件に至る間の補完を、自分なりに妄想して書いてみたいというだけの話
なんですけどね(笑
全て読んだ方は色々言いたいことがあるでしょうが、題にもあるようにこれはあくまでもこれはver.B。
初回プロットとして自分の頭の中にあったのは3つ。
三つとも途中までは共通なんですが、終盤からの展開が分岐する仕様となっております。
まず今回のバッドエンドルートのVer.B(バッド)
終盤で実は『私』が来ヶ谷唯湖じゃないという超展開をするVer.F(フェイク)
コイツに関してはまぁ、さすがにアレだよなぁと思ってプロット段階で破棄しましたが、もうひとつのバージョンは恐らく、
これが上がる頃には完成してウチのブログにうpられていると思われます。
来ヶ谷シナリオといったら二つのエンドが唯一あるヒロインですからね。
考察を書いたりと思い入れがあるので、このような実験をさせて頂きました。
OKしてくださった神主あんぱんさま
そして今回リトルバスターズの簡易メモで、マップを参照させていただいた神海さま。
挿絵を描いていただいたごすさまにこの場を借りて感謝をm(_ _)m
それからというもの、来ヶ谷唯湖の寮部屋を拠点に、私の校内の探索は毎日のように行われた。
初めに確認した『来ヶ谷唯湖』という女性徒。彼女の席に隣接する生徒の寮部屋から一つずつ潰していくという
地味な作業からのスタートだったが、目的意識があるだけで孤独という寂しさは何とか紛らわすことができていた。
ベランダのガラスを壊すには、教室にあったダンベルセットの中から、長さ30cmほどの鉄棒を失敬して使わせてもらっている。
鉄棒を振り回して無人の学校を徘徊する少女―――
想像してみるとただの不良少女のようだが、やっている事はその通りなので言い訳も出来ないなと無理に笑う。
まだ半分ほどしか“作業”は進んでいない。今のところ来ヶ谷唯湖と同様に、例外的に人間の匂いが残存している寮部屋は、
神北小毬、西園美魚、棗鈴、能美クドリャフカの4人ということを確認できていたが、来ヶ谷唯湖ほど完全に部屋が残っているところは
一つもなかった。
神北小毬の部屋は、半分以上が虚無の浸食を受けたような惨状だった。あるラインを境にして、いかにも女の子らしい部屋が
飾り立てられているのに、片側は空き部屋のような有様。西園の部屋は表層の作りはちゃんとしているのに、机や本棚を漁ると
職員室と同じでカラッポか、白紙の束を束ねた装丁の小説が並んでいた。
能美や棗鈴の部屋も似たようなものだ。
進捗は斯様に足踏み状態を維持したままだが、幸か不幸か、この作業の最中、私は“ジョーカー”を拾っていた。
ババ抜きの『ハズレ』か、ポーカーで力を発揮する『当たり』かはまだ見当が付かないが、何らかのヒントを提示している事は確かだった。
来ヶ谷唯湖を含めた例の四人が、同じ写真を所有していたのだ。
多分、それぞれが最も大切に保管できる場所、見栄えの良い最良の場所を選ぶように、あるものは仕舞われ、あるものは飾られていた。
何かの記念なのか、10人の男女が和気藹々と写っている。裏には『リトルバスターズ』と記載され、部活か何かのメンバーで
あることは容易に想像できた。
写真には私も映っていた。
巨漢の男と、いかにも清楚な印象の女性に上下を挟まれる形で、可愛らしく顔だけを覗かせて微笑んでいる。
まともな写真はこの世界ではそれ一枚きり。アルバムを時には見かけることもあったが、収められた写真のすべてが真っ白の紙切れと
化していた。何故かは分からないが、『何か』がこの写真にある―――ということを如実に物語っている。
彼らがどんな連中なのかはこの写真だけでは察することができないが、少なくとも私は幸せだったのだろう。
こんな表情で笑い合える友人が居たのかと思うと、我が事ながら羨ましいと今の自分を省みて、つくづく思い知らされる。
一日の終わりになると、私は毛布に包まりながら、来ヶ谷の寮にあるその写真を眺めては物思いに耽るようになっていた。
どれかは分からないが、多分この中に来ヶ谷唯湖も居るはずだった。
それはつまり、来ヶ谷唯湖と私は面識があったということになる。
私達は、一体どんな話をしたのだろう・・・?
* * * * * * * * * *
何日かが経過した。
昨日、女子寮を一通り終えることができた私は、その日ようやく男子寮に手を付けていた。
座席表の男女を調べる程度なら二、三日で事足りるだろうと当初は楽観していたが、物事には常に山あり谷ありだと、
私は改めて思い知らされる。
全員が地上階であれば苦労などしないのだが、それが上階となると話は別だ。基本的に鍵の掛かった寮部屋への侵入は、
ベランダをつたって二階、三階へよじ登るという行程が必要となる。右手の傷が癒えてない私にとって、この作業はかなり堪えた。
当然、正攻法で正面突破を試みたこともあったが、力任せの破壊や、針金を曲げての鍵の開錠など、体力と時間の浪費だと早々に
悟って以来、専ら壁登りが主流である。
寮部屋がカラッポであれば一瞥して戻れば良いだけの話だが、部屋の内装が保存されていた場合、一通り調べるという作業が
これに加算される。このときほど人の所有する物品の多さに嫌気がさすことはない。一部屋だけで長いときでは半日以上を費やすのだから、
調査は女子寮だけで相当の日数を消費していた。
今回の男子寮の探索で、調べていた生徒が初回から三階であると知ったときの私の気分が如何ほどであったかは推して知るべし―――。
後に回そうかとも思ったが、どうせ、いつかはやらなければならないノルマである。やるなら早めの方がいいと覚悟を決めて、
三階に住居を構える他の二名の部屋も、まとめて片付けたのが数分前のことだ。
先日失敬した水筒から、水が咽喉を伝うのも構わずごくごくと飲み干して、私は息を吐く。作業時には当たり前となって久しい
ジャージの袖で汗を拭うと、大した収穫もなく無駄骨に終わったことを、勤めて忘れてしまおうと次の作業に取り掛かった。
手際は慣れたものだ。傍に置いたバッグから寮の玄関口に張られていた部屋割り名簿と、教室にあった座席表を見比べては、
先ほどの部屋の留意点を書き込んでいく。
その姿は一介の女学生とは思えないほど凛々しいけれど、肌に載った疲労の色は隠しようがない。
孤島に一人だけ取り残された人間がはじめに飢えるのは、人との触れ合いだといわれている。寮部屋を探索する目的が、
その意味合いを変化させつつあるのもそこに原因があるのだろう。例の教室と、生徒たちの関連を解き明かすことよりも、
誰か他に人が居ないかを主眼に寮部屋を放浪している自分に気付いたのは、つい最近のことだ。
記憶喪失による精神的な不安と、「私は誰であるか」という強迫観念。
閉塞した世界と支えのない孤独感が、その気持ちを更に助長していたのだろうが、焦燥は強くなるというのに得られる成果は微々たるものだ。
ベランダをつたって上り下りする私の寮の探索と比べ、日常そのものは平坦で起伏がない。同じ日を何度も繰り返しているような、
奇妙な既知感に囚われてしまう。
そのためか、私がこんな目に合って、いったい幾日経過したのか・・・実を言うと、もうほとんど憶えていない。
降り注ぐ光のカケラは止む事を知らず、同じ風景と、同じ日常の繰り返しに、当の昔に私の心根は折れていたのかもしれない。
感情の限り叫んで、人を求めたこともあった。
「何でこんな目に・・・」と、一日中来ヶ谷唯湖の部屋から出なかったこともある。
私はもう知っている。ここには本当に、私一人しかいないという事を。
けれども、人を探さずにはいられない。暇を見つけては校舎の中も探してはいたが、確率的に誰かが居るとしたら寮部屋以外に
考えられなかった。
不毛と知っていながら、こんなことを続けている私は馬鹿なのだろうか。
それとも、どこかで狂ってしまったのだろうか。
窓を壊しても、部屋をめちゃめちゃに荒らしても、何事もなかったかように翌日にはすべてが元に戻っている事象を目撃してからと
いうもの、どこかで私の心のバランスは崩れ始めていた。
負担ばかりかけていた左腕は小刻みに震えていた。
それが伝染して、震えが身体を覆っていく。
誰でも良い。
ただ・・・誰かと逢って話しをしたかった。
バラバラに壊れそうな部品を繋ぎ止めている私の糸は、今にも切れてしまいそうだ。
それでも平静を装い、次の目標となる男子生徒の部屋を探していたところ、ある名前で目が止まる。
棗恭介・皆川早瀬 312号室
どこかで見たことのある名前だった。
私は最近の記憶を掘り起こそうと、感傷的になっていた気持ちを切り替える。
棗恭介・・・・。棗―――そう、棗鈴だ。
珍しい苗字からも、棗鈴と血が繋がっていると推測するのもあながち的外れではあるまい。調べてみても損はないと判断した私は、
とりあえずの目標を見つけることができて、ほんの少しだけいつもの平静さを取り戻す。
こういう収穫のあるときはいい。思考を循環させている間だけ、嫌なことから目を背けていられるから。
それにしても、例の教室の生徒にしか目が廻っていなかった自分が憎らしかった。
部屋番号からして三階だろう。軽く眩暈を覚えるが、そこはグッと堪えて名簿をバッグに仕舞い、小脇に抱えると、一応、
部屋のドアが開いていないかを調べに階段を上って三階へ向かう。
一度として開錠された状態の寮部屋というものを拝んだ事はないのだが、ベランダをよじ登るという重労働を回避する可能性が少しでも
あるのだ。この階段を上る程度の労力で済むのなら、確認してみる価値はある。
疲弊した身体に鞭打ちながら、私は一段、また一段と足を運ぶ。
それにしても、男子寮の名簿は見ていたのだが・・・棗恭介を見過ごしていたことが、どこか腑に落ちなかった。まぁ、棗鈴の
『家宅捜査』を行うまでは、あまり気にも留めていなかった苗字なのだから、見過ごしていたのも当然といえば当然なのかもしれないが・・・・。
例の写真には確かに兄妹らしい二人の姿が写っていたと思う。いかにもやんちゃそうな男と、どこか困った表情のポニーテールの少女。
棗鈴と棗恭介があの二人だとするなら、私と能美クドリャフカの合わせた四人が、あの写真の中で顔と名前が一致したことになる。
女生徒の来ヶ谷唯湖、神北小毬、西園美魚で女子の数は合うから、残った男子生徒3人を見つけることが今後の課題であろう。
これがすべて終わった先にある予感を、私は勤めて見ないようにしていた。これだけの時間と労力を費やしていながら、得られたものは
友人と思われる9人の存在を映した写真一枚きり。すべてが徒労に終わるであろうことをどこかで悟っていても、止めることなど私に
できるはずもない。
そこで足を留めてしまったら、私は『現実』を見つめなければいけなくなる。
過酷な現実を目の前にすれば、私の心はきっと死んでしまう。
だから私は、あの写真に依存する。
一日の終わりになると、あの中の生徒達との日常を空想しては、現実から飛翔して、もう二度とこの世界へ舞い降りてこないようにと
切に願って布団を被る。漂流したこの世界の方が間違いで、きっと夢か何なのだと自分に言い聞かせて・・・・。
どんなに強くあろうとしたって、私はちっぽけな一人の少女でしかない。力が強かろうが、どんなに賢かろうが、ひとりきりの自分を
満たす糧にはなりはしない。
こんな現実と今こうして付き合っているのだ。
少しくらい夢を見たっていいじゃないか・・・
舞い落ちる光の粒子は、とうとう寮の内部にも浸水していた。
どこから落ちてくるのか、ひらひら、ひらひらと私の目先を過ぎっては、小さな夢を灯しては消えていく。
空ろに沈む私の瞳は、やがてカケラの残骸に吸い寄せられる。
リトルバスターズの面子と、私の間にあった関係はどのようなものだったのだろうかと想いを馳せていると、うつらうつらと舟を漕ぐように、
気付けば私の意識はどこか遠くに流されていた。
私を苛めていた孤独と疲労が、とうとうピークに達してしまったのかもしれない。「こうであったら良いな」という過去を妄想しては、
現実から目を背けようとする何かが、私の『何か』を断ち切ろうと首に手をかけていた。
私が笑っている夢
私がささやかな恋している夢
私が多くの仲間たちに囲まれて、日常の学校生活を過ごす夢
とても甘くて、魅惑的な夢だ。いつまでも続けばいい。あの写真の仲間達に囲まれて、どこまでもどこまでも、楽しく平穏な世界を
ぐるぐると、ぐるぐると・・・・・・・・。
死ぬまで妄想の世界で生き続けれると言うのなら、それは確かに幸せなことなのかもしれない。
ふうっと訪れる陶酔に身を委ね、静かに闇に落ちそうになる私の背中を、誰かがそっと抱きしめたような気がした。
―――そんな世界、僕は認めない・・・・!!―――
誰だったろう?
以前誰かに言われた言葉が木霊した。
華奢な体つきをしているくせに、人一倍健気で、誰よりも優しくて、強い人。
だから私は・・・。
私は・・・・・・・
「・・・どうしたのだろう・・・?」
数日に渡る強行軍で、肉体的にも精神的にも限界に達していたのだろう。階段の途中で崩れるように倒れていた私は、
夢心地の頭を振って起き上がる。
何かを思い出しかけていたような気がしたが、それももう、夢と共に曖昧なものとなっていた。
無理な体勢で倒れていた為か、節々が痛い。散らばった所持品を拾い集め、廊下の窓から外を見回すと、いつの間にか三階まで
来ていたようだ。夢遊病者じみたあんな状態で、よくここまで来たものだと呆れてしまう。
ふと横を見れば314号室は目と鼻の先だ。
この部屋にもやはりあの写真があるのだろうか・・・・。
錠が掛かっていることを覚悟して軽くノブをひねると、拍子抜けるほど簡単にドアが開く。息を呑み、私はゆっくりと中を窺った。
光の届かない深海のように、深い闇が部屋を支配していた。
目を凝らすと、うっすらとだが二段ベッドらしき輪郭や、勉強机、平積みされた数冊の雑誌が識別できる例外的な空間だ。
どうやら棗鈴の血縁者という仮定もあながち間違いではなさそうだ。
例外者の中では私が見つけた初の異性でもある。新たな発見があるかもしれないと期待に胸を膨らませるが、こう暗くては
作業に差し支えが出る。
手始めに遮光カーテンをなんとかしないと・・・
部屋に足を踏み入れた私のすぐ後ろで突如ドアが閉まった。
慌ててドアを振り返るが暗くて何も見えない。おおよその見当で延ばした私の腕は虚空を薙いだ。
「・・・・・来ヶ谷・・・か?・・・どうやってここに?」
男の声が響いた。
人間の声だ。
記憶を失った私にとっては、“生まれて初めて聞く”他人の声。
一人じゃないことの嬉しさが全身を駆け巡るが、男の言葉を反芻していくうちに、私はゆっくりとだが醒めていく感覚を憶えた。
繋がった先の『ソレ』と自分を照らし合わせて、何かが鮮明になっていく。記憶の奔流と、混濁した感情。
頭の中が割れそうに痛むのを堪えて、確定した私という個体の正式名称を口にする。
「私が・・・・・・・・・・来ヶ谷・・・唯湖なのか・・・・・・・・・」
じゃあ、例の教室で無意識に自分の机に座ったことは一つの必然だったのか?
鍵と携帯が放置されていたのは、記憶喪失前の私が置いていただけ?
じゃあ、あの例外的な空間は・・・・
嵌り続けるピースの数は膨大に膨れ上がる。
圧倒的な物量に堪えきれず膝を突き、それでも私は男の顔を見ようと闇に目を凝らす。
「お前は誰だ・・・・・棗恭介か?」
質問の意味を巧く把握できなかったのだろう。
しばらくの沈黙が終わると、男は意外そうな声を上げた。
「・・・・おいおい、まさか完全に記憶をなくしているのか? そんな状態でどうやってあの世界を持続させて―――いや、そうか・・・。
それで俺の部屋に繋がったというわけか。記憶喪失にでもならなければ、お前が好き好んで俺の部屋にくるはずもないし・・・・
整合性は確かに取れるが・・・・」
「・・・・・・何が言いたい!? なにを言っている!?」
一人納得する男に苛立ちを隠せない私は、奥へと進む。
部屋の隅に浮かぶシルエットが、もぞりと動いた。
「来ヶ谷。お前の世界はもう終わりを迎えている。そこにあるのはただの『残骸』だ。“こっち”と繋がったのは、綻びの隙間を
巧く掻い潜れたからだろうという仮定しか出来ないが・・・・恐らく、お前の世界が完全に終わりを迎える前兆だろう。
・・・今のお前に話しても理解できないだろうが、お前の願いにはそもそも無理があったんだよ。『永遠』を願ったところで
破綻が生じる事は分かっていたはずなのに・・・・どうしてお前はその世界を願ってしまったんだ・・・」
分からない。
彼が何を言わんとしているのか私には理解できない。
「他に、願うべきものがあっ・・・た・・・ろ・・・。両親・・・関係・・・の修・・・・・・・・・・の・・・・に・・・」
「待ってくれ! 聞こえない! この世界はまやかしなのか? どうすればここから出られる!?」
男の声が遠い。物理的距離は3mもないというのに、歩み寄る私と男との距離はいくら経っても縮まらなかった。
あと、少し・・・あと少しがもどかしい。
「・・・・な・・・おえ・・・・き・・・。・・・わ・・・す・・・・れ・・・」
手の先が男に届いたのは直後のことだ。布地と思し手触りを頼りに私は一気に男を引き寄せる。
聞きたい事は山ほどある。そして男はそれを答えれるだけの知識を持ち合わせているらしかった。まずは顔だ。
写真の男なら、リトルバスターズについても聞けるだろうしこちらとしては好都合だ。
私はカーテンを力任せに引き毟る。レールごと盛大に剥がれて、外光が闇を駆逐する。
そうして目の前にあったのは、襤褸と化した唯の布切れだ。
男はおろか、部屋の中に確かにあったはずの二段ベッドもなければ、男のもとへ向かう最中によけたはずの、ゴミや雑誌の山は
陰も形もなくなっている。
狐に抓まれた面持ちの私は、辺りを見回して更に呆然とする。
314号室だった部屋は廃墟と化していた。
天上や側壁は失われ、吹きさらしの空からは、光の飛礫が舞い込んでいた。
いや、314号室だけじゃない。隣も、その隣も・・・・男子寮はおろか、数十メートル先にある校舎、女子寮、体育館。
何から何までが廃墟一歩手前の零落ぶりを晒している。
この世界の終わりの前兆―――
男は確かにそういっていた。
それが・・・・これか?
漂流していた学校の敷地はとうとう闇に飲まれ、グランドの半分近くが削れてなくなっている。侵食速度は以前と比べ物にならないほど
速く、数時間もすれば、すべてがあの闇に覆われるだろう。ここでオメオメしてたら私も崩壊に巻き込まれる。
314号室前に転がっていたバッグを抱えて、私は寮部屋を後にした。
とにかくこの世界から抜け出す方法を探さなければいけない。
最後に男はなんと言った?
なお・・え・・・・・直枝・・・・・
どこかでそんな名前を見かけたような気がして、座席表と、寮の部屋割り表を私は取り出した。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なんだ・・・・・・これは・・・・?」
プリンターで印刷された紙面の文字は、数十年の時を経たように擦れていた。名前を確認しようにも、うっすらと見えるのは
罫線くらいのもの。私の座席の場所がどうにか判断できる程度の解像度で、誰かの名前を特定するなどできるはずもない。
ついさっきまで普通の紙であったものが、どうやったらこうまで劣化するというのだ。
せっかく、何かが見えはじめたというのに・・・・!
私は力任せに地面に叩きつける。その一撃が紙書類の寿命を終わらせた。
チリ屑と化した紙吹雪は上空を舞い、それは突然、光の粒子となって虚空へと還っていく。
唖然とする光景を目の当たりにして、私はようやく光のカケラの正体に気付くことができた。地面も、草木も、建物に至るまで・・・・。
降っていたと思っていた光の粒子は、この世界を構築していた物質そのものなのか。
作り物の世界。その残骸の中で彷徨っていたのがこの私・・・来ヶ谷唯湖だったと言うわけだ。じゃあ私も誰かに創造にされた
作り物なのだろうか?
可能な範囲で自分の身体を調べてみるが、光の粒子が私から漏れ出す気配はない。少しだけ安堵するが、状況は何も変わってなどいない。
何か・・・何かできることはないかと思考を巡らせる。
直枝という人物の手がかりは何もないといっていいが、ある程度の推測は可能だ。リトルバスターズのメンバーの一人とするならば、
あの教室のどこかにそいつの机があるかもしれない。運がよければ所持品を見つけ・・・・そして更に運がよければそこから脱出する
手段―――。
常識的に考えて、そんなご都合的な可能性はゼロだとは分かっている。
けれど、動かなければここで屍を曝すだけだと走り出す。
例の教室はまだ健在だった。隣接する教室が既に朽ちているというのに、ここだけ日常の息吹を保管している。
区切られた境界を潜るように、私は教室の中へと舞い戻っていた。
窓の外から見える世界の終わりを告げる光は、その数を何千、何万と増やして一面を真っ白に塗り潰している。
チラホラとその光に混じって、遠い彼方の風景が二重写しに霞んでいた。
季節は初夏だろうか。
暑い日ざしが差し込み、木々がその緑を深めている。
白く塗られたキャンパスの先には、私の見知らぬ世界があった。
この世界はもう崩れ始めているのだ。このままここで息を潜めていれば、もと居た場所へと帰ることができるのかもしれないという
誘惑が過ぎるが、私は大きく首を振る。
違う。
まだ帰れない。帰ってはいけないと本能が警告していた。
私は何かを忘れている。この世界に何かを置き忘れたままだ。
戻った瞬間それは消えてしまう。
それではダメ。
それではこの世界を願った・・・・・・・意味が・・・・
今・・・私は何を口走った?
あの男と出会ったことで、何かが・・・・忘れていた記憶の断片が、ここに来て私の中に生まれつつあるのだろうか。
かつては他人だと思っていた来ヶ谷唯湖。その席に私は座り、必死に何かを思い出そうと努力する。そう、私は何かを願ったのだ。
全てをかなぐり捨ててそれだけを願った。それだけあれば他はもういらないとさえ祈った自分の気持ち・・・・。
あったはずなのに・・・・
痛いくらいに拳を握る。
思い出せないことが自分の罪であるかのように髪をぐしゃぐしゃにすると、声にならない絶叫を上げて私は机を蹴り飛ばした。
愚か過ぎる。
願いをした本人が全てを忘れているというのに、その願いだけが一人歩きをして、こんな世界を未だに残し続けているという事実が。
この世界は、私に何かを教えようとしている。そうでなければ、こんなにも無残になった状態で存続し続ける意味がない。
それとも無意識に、私という主体がこの世界に今に至るまで何かを願い続けているのかどちらだろう。
ダメだ・・・考えても分からない。
力なくうな垂れる私の顔はとうとう下を向いた。
携帯電話があった。
来ヶ谷唯湖の・・・私の携帯電話が、机が蹴り飛ばされた拍子に転がっていた。
全身に鳥肌が立つ。
藁をも掴むように私はそれを手に取った。
そうだ。あったはずだ。メールで、私は誰かに宛てて恋文を送り続けていた。
確信する。私が思い出すべき事はそれ以外にありえない、と。
私はゆっくりとメール履歴のボタンを押した。
受信メールはありません
たった一文の報告に、私の思考は停止した。
そして、ただ可笑しくて笑い出す。
そんな馬鹿な。あるはずがない、何かの間違いだともう一度、履歴ボタンを押す。
受信メールはありません
・・・・・・ありえない。
ありえない。ありえない。ありえない。
消した記憶はない。机から落ちた程度でメモリが飛ぶとも思えない。
送信メールの履歴も調べてみるが、こちらもどういうわけか『送信メールはありません』という無機質な文面が羅列されている。
電話の着信履歴、リダイヤル、友人のメールアドレスや電話番号の全てが初期化されていた。
購入したての市販品のようなものに成り下がってしまったそれを取り落とし、ただ無言で私は首を振る。最後の希望が枯れ落ちてしまった。
それを合図に、守られていた教室、机、私品の多くから・・・・光が洪水となってあふれ出す。
手遅れだったのだというには、あまりにも『それ』は近くを通り過ぎていた。
私が・・・来ヶ谷唯湖が思い出すべきだった何かを連れて、世界は徐々に白に埋もれていく。
こんなことで終わるのか?
この程度で私は何かを失ってしまうのか?
いやだ、いやだ・・・・!
気力を揺り起こして立ち上がると、もう不要とは分かっていたが、何かを閉じ込めていた携帯を、“遺品”を手に取るように
大事に抱えて私は教室を抜けた。ドアを抜けると同時に、他の教室と同様の姿に聖域は崩れ落ち、置いてあった私のバッグも、
それの余波を受けて光となって消えた。
よろよろと立ち上がる私の手元に残ったのは携帯と、三つの鍵束。
記憶を保持していた頃の、来ヶ谷唯湖の遺留品とも言うべきそれが、私に与えられた唯一の活路だった。
鍵の一つは寮の部屋としても、残りの二つは私に何を示唆しているのだろう。
一つは寮の鍵と似た形状で、残りの一つは3cmほどの長さのチャチな造りをしている。
使用場所は皆目見当も付かないが、何かの役に立つかもしれない。ポケットに仕舞うと、渡り廊下を抜けて、私は対向側の校舎へと
移動する。闇の侵食は、程なく向かいの校舎を飲み込んだ。気付けば寮側に立っていたこの校舎しか残っていない。
廃校同然のここが、最後の砦というわけだ。
だが、まだ全てが終わったわけじゃないと私は自らを鼓舞する。
崩壊が始まって、全てのものが崩れ落ちているという事は、逆に考えればチャンスでもある。
寮や例の教室のある校舎は一通りの調査を行ったが、寮側にある校舎は優先順位が低かったこともあり、それほど調べたわけではないのだ。
仮にあの教室のように、例外的な空間が存在するのであれば、今のこの状況なら、記憶を喪失した私にでも重要性が視覚的に
把握することができる。要は崩壊していない場所や物を探せばいい。
見つけるのだ。この崩壊の跋扈した世界で、来ヶ谷唯湖の想いを保持した『何か』を。
今の今になって、ようやく私は疑問の氷解音を聞いていた。
答えは単純だったのだ。
この世界の影響を受けずに残存していた例外的な空間や物は、私と繋がっていた。
リトルバスターズの写真
その中で笑う友人達の部屋
私が通っていた教室
来ヶ谷唯湖である私の部屋
全部、全部意味があった。
無意味なものなんて一つもなかったのだ。
ガラクタと吐き捨てた、あの教室にあった物品も突き詰めていれば、きっと何かの役に立ったかもしれないのに。
一階の廊下をひた走っていた私は『それ』を見つけていた。
周囲と比較して充分綺麗なドア。影響を受けていない証拠だ。
「放送室」というネームが貼られているが、果たしてこんな場所に何かあるのだろうかと首を傾げてしまう。しかも、当然のように
施錠されたドアはビクともせず、崩壊を起していない代わりに、私をも締め出して盤石の鉄壁を誇っていた。
裏から何とかならないかと外に向かおうとしたが、玄関口で生じた鈍い音が、私の勇み足を押し留める。ぐらりと校舎が揺れたのは
その直後だ。
玄関左手の校舎下の地表がとうとう闇に食われたのだ。寄りかかる土台を失くした校舎は自重に負けて半壊した。
体勢を低くしていた私には幸いにも大した怪我はなかったが、振動でもんどりを打った拍子に足首を挫いていた。
震災の第一波が収まるのを確認して、ひょこひょこと足を引き摺りながら窓に向かうと、私は身を乗り出して外を窺う。
あたり一面は闇の海と化していた。
空には崩れ落ちた天蓋がぽっかりと開いている。それはもう空というよりも、きらきらと光る豪華なシャンデリアを叩き壊した
瞬間の映像だ。ぶちまけられた光の粒が闇の黒に映えて、思わず見惚れてしまうそうだ。
天も地も周囲の建造物も根こそぎ消滅している。
食べ残しはここだけというわけだ。
あまり考える時間もないというのに、この堅牢なドアを攻略する方法で、ろくな案が浮かばない。寮のベランダから侵入というような
アクロバットな小技はやりたくても、右手は痛むし、足首は痛い慢心創痍状態。
移動も無理、力技も無理ときてはさすがの私も手の打ちようがない。
「もうここまでかな・・・・」
ニヒルなタフガイなら、ここでタバコの一つでも燻らせるのだろうが、生憎と私の手元に、そんな物は・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
サイドポケットに手をやると金属特有の硬質な手触りがあった。
取り出してみると鍵の束。
一つは寮の鍵。
そして一つは同系の鍵。
まさかな、とは思いつつも、その鍵を錠に差し込むと見事に嵌り込む。
そのまま半時計方向に回すとカチリ―――という小気味いい音を立てて部屋は私を招きいれていた。
狭い部屋だ。
もともと放送だけを目的としているであろう部屋に、マイクやら面倒そうな設備がこれでもかと突っ込まれているのだから無理もない。
奥には電子ピアノらしきデカブツが鎮座しておりなかなかに壮観だ。
放送室に入ると同時、朝からずっと酷使し続けた身体はもう限界だった。倒れこむようにフローリングの床に身体を横たえると、
私はそのまま身動き一つ取れなくなる。
床の冷たさがほてった身体に心地いい。妙な達成感を憶えて、私はこの世界で初めて作り笑いじゃない、本当の微笑いを浮かべることが
できた。
ここが私の終着点。
そして、多分・・・記憶喪失以前の来ヶ谷唯湖が一番の想いを込めた場所。
記憶喪失以前の私がここに何を感じ、何を経験して、何をしていたのかは分からない。
分からないけれど、それはきっととても大切なことだったんだろう。
闇と光のカケラに飲みこまれもせずに、最後までここが残ったのも偶然じゃない。
“ここを中心にして作られた世界”だからこそ、最後に残ったのがここだったというだけなのだと思う。
それが分かっただけでも、私は満足だった。
胸に酸素を充填すると、やがて私は大きく息をつく。
一人の少女によって創られた世界は、とうとうその限界を迎えていた。
不完全で、不恰好だったカタチは歪み、『世界の中心』である放送室へと闇は進行する。
壁が光のカケラとなって消えていく。
床も、機材も、そして、私自身も・・・・
恐くはなかった。
徐々に埋没する足はその存在感を失い、やがて腿、腰、胸を覆い・・・
最後に私の顔はとぷりと沈んだ。
結局、直枝という人物だけがよく分からなかったなと、私は感慨深く呟いた。
男なのだろうとは薄々とは感じていたが、やはりそれが誰なのかを理解することができないまま、来ヶ谷唯湖である『私』が、
私ではなくなることが少しだけ心残りといえた。
混濁した意識の中で、私は奇妙な夢を見る。
私が誰かに恋をしているという夢。
それは叶わぬ恋であり、私自身も分かっている悲しい夢。
とても儚く悲しいけれど、分かっていても、やはり私は彼を好きになるしかなかったんだと諦めたように小さく頬笑う。
けれどそれは夢。
どんなに苦しくて、恋しくても、それは夢。
だから忘れてしまおう。
悲しかったことも嬉しかったことも、全部この夢に詰め込んで―――
あとがき
|ω・`)
うん、多分一番空気読めてない作品だと思います。
というわけでまずは一言言わせてください。
スンマセンでしたー!!!!!!orz
さて(ぉ
今回のSSは、ウチのブログの『二次創作考察小説』というSSの番外編的位置付けの作品だったりします。やれることなら来ヶ谷の
補完的な作品もやりたいなと思っていた自分にとって今回の来ヶ谷祭はまさに渡りに船ということで投稿させていただきましたm(_ _)m
基盤にあったのは来ヶ谷シナリオの終盤からラストへの件に至る間の補完を、自分なりに妄想して書いてみたいというだけの話
なんですけどね(笑
全て読んだ方は色々言いたいことがあるでしょうが、題にもあるようにこれはあくまでもこれはver.B。
初回プロットとして自分の頭の中にあったのは3つ。
三つとも途中までは共通なんですが、終盤からの展開が分岐する仕様となっております。
まず今回のバッドエンドルートのVer.B(バッド)
終盤で実は『私』が来ヶ谷唯湖じゃないという超展開をするVer.F(フェイク)
コイツに関してはまぁ、さすがにアレだよなぁと思ってプロット段階で破棄しましたが、もうひとつのバージョンは恐らく、
これが上がる頃には完成してウチのブログにうpられていると思われます。
来ヶ谷シナリオといったら二つのエンドが唯一あるヒロインですからね。
考察を書いたりと思い入れがあるので、このような実験をさせて頂きました。
OKしてくださった神主あんぱんさま
そして今回リトルバスターズの簡易メモで、マップを参照させていただいた神海さま。
挿絵を描いていただいたごすさまにこの場を借りて感謝をm(_ _)m
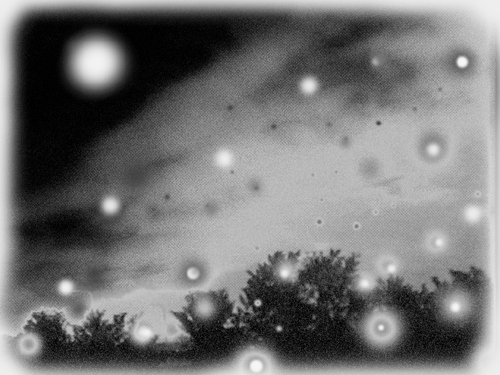 初めに見たものは虚空を舞う幾千もの光だった。
風に乗って舞う綺羅星の粒は、一面を銀世界に染め上げている。雪か何かだと誤解していたが、晩春を思わせる気候と
樹木に息吹く緑の青さが、論理の矛盾を突きつけていた。
落ちてきたその欠片を私は掌で受け止める。
冷たくもなければ、暖かくもない。肌に触れると瞬く間に無に帰した。
「これは何なのだ?」という疑問の答えは出ないまま、広い敷地にポツリと佇んでいた私は小さく息を吹き返して、何度目かの溜息を吐く。
今まで何をしていたのだろうと思い起こそうとして、以前の記憶が綺麗に白紙になっていることに少なからず動揺したのはつい先ほどのことだ。
日時も、場所も、自分の名前さえも忘れた境遇において、唯一分かっているのは『私が女である』というどうでも良いことだけだったというのも
情けない。
身につけている制服からどこかの女学生であり、そしてその私が通っているところが、私の眼前にそびえる洒脱な校舎であることだけは
なんとなく察することができた。
梅雨時を思わせる薄暗い雲の暗幕は、昼とも夕刻ともとれそうで、おおよその時刻を推測することすら叶わないが、早朝や深夜でないこと
だけはたしかな筈だった。
なのに、どうしてあたりはこんなにも静かで、私以外誰一人としていないのだろう。
無音過ぎて耳が痛い。
ここで立っていても意味がないことだけは確かだ。手始めにポケットに手を入れて所持品の確認をする。
何かの手がかりになりそうな物があればと期待したのだが、生徒手帳は元より、記憶に繋がりそうな物は何一つとしてない。
おとなしめの柄のハンカチとポケットティッシュが一つずつ。 財布は持ち歩かないタイプの人間なのか、平日の学校では
充分と思われる小銭が数枚あるだけだ。
現実はこんなものだと肩をすくめると私は一直線に校舎へ向かう。
「おい、誰かいないのか!?」
体育館と思しきアーチ状の建造物を手近の窓から覗いてまわるが、中はガランドウで、ワックスで綺麗に磨かれた床が鈍く光る他は、
これといって目を惹くものはなさそうだ。
そのまま歩を進めると中庭と思しき場所に出た。渡り廊下を挟んで校舎が二つある造りで、こうして間近で見ると意外と大きい。
どちらから探索するか一瞬迷うが、何とはなしに右の棟に足を向ける。
「失礼する」
一階の『職員室』と表札の掛かった部屋はやはり無人だった。
生徒数十人を抱えるであろう担任がここにひとところ集まり、翌日の授業準備や、成績を付けたり、雑務をこなす場にしては異質すぎるほどに
整頓されている。遠慮がちに適当な机の引き出しを開けてみるが中はカラッポだ。そのまま下段の二つも調べてみたが何もない。
書庫棚に整然と詰め込まれたファイルの背表紙は何のラベリングも無く、もしやと思い一冊取り出してパラパラとめくってみた。
「・・・記憶喪失で右往左往している乙女に対して、この冗談はちょっとキツイな」
真っ白のページだけが最後まで続いていた。
次のファイルも、次のファイルも・・・・・・・・・・全部が白紙だった。
窓の外は相変らず光の粒子が淡い燐光を発している。
まるで世界の終わりのように―――
職員室を飛び出し、私は走った。
階段を駆け上がり、二階、三階、四階と顔だけ覗かせたが、廊下に誰もいないことが分かると上を目指す。
屋上に続く階段の終着点にたどり着く頃には、軽く上気してうっすらと汗をかいていたが、私は気にも留めず外へ続くドアに手をかける。
手製で『屋上 立ち入り禁止』と書かれた紙のぶら下がる謹製のドアは重く、ノブを回してみると鍵が掛かっている。
蹴り上げてみるがビクともしない。
舌打ちして周囲を見回すと、目線の少し上に人が一人、何とか潜れそうな窓が見えた。
一瞬躊躇したが、それを蹴破る。破片を取り除き、注意して屋上に降り立つと私は下界を見下ろした。
確かめたいことがあったのだ。
現実ではありえない現実と、体験した不可解な状況。この閉鎖した世界と、私の混乱した思考を打破する何かがあると思ってここに来た。
来たはずなのだ。
それなのに・・・・・・・・
そんなはずはない、あるはずがないと、駄々っ子のように私はイヤイヤと首を振る。
乱れた髪が顔に張り付いて、身体が小さく戦慄いた。
学校の敷地より先の物がことごとく消失している。
校門より先は黒い空間が蠢いており、その中でこの学校だけが孤島のように浮いている。端の方は目を凝らすと、少しずつだが
削れているようだった。ぽろぽろと零れて、闇が世界を侵食していた。
「・・・・・・・・・馬鹿馬鹿しい」
鼻で笑おうとして私の顔は歪んだ。夢か何かだと信じたかったが、汗で張り付いた服の肌触りと、血の気の引いた我が身がどこかで
何かを悟っていた。
光が積もっていく。
どんどん、どんどん。すべてを覆い尽くすように・・・。
緊張した肺に酸素を取り込む行為は予想以上に難航した。自らを叱咤するように一度頬を叩き、挫けそうな気持ちに喝を込める。
異常な事態に巻き込まれている事は理解したが、頭と気持ちが未だ混乱していた。
どこか落ち着ける場所で、気持ちを整理する時間が欲しい。今の私には、この屋上の光景は刺激が強すぎた。
それに・・・・光の粒が私に触れる都度、この学校同様に何かを削られているような喪失感を味わった。
出来れば外に居たくない。
重い足取りで再び校舎に戻る。一時間にも満たない短時間で起った訳の分からない出来事の数々に、私の頭は大分疲れていた。
下りる段数を数える気も起きず、適当な階の適当な教室に入ると、目に付いた机の椅子に腰掛けた。
「さて、どうしたものか」
天上を見上げて私は頭に腕を載せた。独り言を呟いてみたものの、それに対する解はおろか、芥子粒ほどの情報すら仕入れていない私に、
いったいなにが弾き出せるというのだろうかと苦笑する。
いっそこのまま眠ってしまえば、すべてが解決しているのではないかという淡い期待が湧いてしまう。少々気が滅入っているし、
ここで寝てしまうことへの抵抗はさほどない。毛布くらいは欲しいものだがと、あるはずもない物品を求めて教室に視線を彷徨わせて―――
私は腰を浮かせた。
あまりに当たり前すぎて、入った時は気にも留めていなかったが、この教室にはどこか人が時間を過ごした匂いとも言うべき煩雑さが窺えた。
わずかに傾いだ机。生徒が立ち上がって、そのまま在らぬ方向を向いた椅子。消してはいるものの、数式や文章痕の残る黒板と、
その下のチョーク受けに積もった色とりどりの粉粒。ホコリっぽい空気。
後ろの生徒ロッカーに残された物は学業用の書物や、何故か一角を占める筋トレグッズの山、不要と思われる携帯ストラップや漫画、
雑誌、その他諸々。
不思議に思い、席を立ってこの階の教室を一通り見て廻ったが、他の教室は職員室と同じだった。機能的に画一化されて、
人の匂いすらしない無菌室のよう。
再び例の教室に戻った私は背中越しに扉を閉める。
理由は不明だが、この一角だけが例外的な措置を施されていることは確かなようだった。
過剰な期待をすると失望した時の反動が大きいと分かっていても、気持ちはとても正直だ。
高まる鼓動を抑えて、まずは教壇の机にぽんっと無造作に置かれた座席表を手に取った。
見知った名前があれば、そいつのロッカーと机にある物品を物色して、芋蔓式に情報を取得しようという心積もりだったが、
無くなった私の記憶を呼び覚ますような名前はザッと見た限りではなさそうだ。
あの筋トレグッズの所有者が、井ノ原真人という生徒のものである事は了解できたが、無駄な知識を増やしてしまったようで妙に腹立たしい。
能美クドリャフカという生徒にも目が行ったが、単に名前が珍しかったからだろう。
原口雄介、三野瀬仲百合、棗鈴、井上和也、直枝理樹、佐々口洋平、小町洋子、神北小毬・・・・・・・・・・
そうそう巧くいくものではない事は予想していたが、現実の壁というヤツは、ほんの少しも私の期待を叶えてはくれないらしい。
この教室が私と何か関連があると仮定した上での行為も、どうやら無駄に終わったようだ。何人かの机やロッカーを覗き込んだものの、
どれもこれも先ほどのような輝きを失い、私にはただのガラクタの山のようにしか見えない。
疲れた・・・・・・・。
失望は思ったよりも私の気力を萎えさせた。
倦怠感と虚脱感が、私の身体に重く圧し掛かる。
やはりここで寝てしまおうかと思ったが、どうやら私も一端の『女の子』らしい。ベッドと熱いシャワーが恋しかった。
汗でべとついた体と、ごわついた髪を何とかしたいという欲求は、こんな状況においてもしっかりとあるようで、なんだか可笑しくなる。
そういえば、この校舎の正面口玄関に学校の見取り図が掲載されていたことを思い出す。たしか隣の校舎を越えたところに女子寮があった。
そこまで行けばそれらしい設備もあるだろう。
教室を出る前に、ふと気になって座席表を見直した。
無意識に座った座席の生徒に、ほんの少しだが興味があった。
来ヶ谷 唯湖
静謐の湖面を思わせるその名前は、凛として美しいけれど、どこか寂しい。
彼女の私品を物色したが、あまり持ち込むタイプの人間ではないようで、目に付く物はさほどなかった。
気になったのは、鍵の束が放置されていたことと、当人のものと思われる携帯電話が無造作に机の中に置いてあったこと。
メール履歴を盗み見たが、友人と面白おかしくやっていたのだなくらいしか窺えない。後半の履歴の多くは恋文のようだった。
最初の数行は読んでみたものの、他人のプライバシーを侵害している背徳感に私は目を逸らす。
外部に繋がる可能性を期待して、警察と消防署に掛けてみたが不通のようだった。メモリから任意の番号を引き出して掛けてみるが、
・・・・やはり不通である。
待機画面に戻すと、ディスプレイには2007年6月20日の文字。
どうやらそれが今日の日付らしい。
鍵の束の方は、自宅のものと思われるものを含めて全部で3つ。ということは、彼女が自宅に帰る前に突発的な何かが起って、
今のような事象が継続しているのではないかという可能性が想像できたが、それが正しかったとしても今の私には何の解決も提示してはくれない。
「・・・来ヶ谷唯湖女史。キミは私を知っていたのだろうか。知っていたらならば教えて欲しかったな。記憶を失う前の私は、
一体どんな人間だったのかを・・・・」
* * * * * * * * * *
女子寮は新館と旧館があるようだった。
ここもどこか無機質で、人の気配がないのも相変らずだ。
外から見た経年劣化の具合の程は、どちらも似たり寄ったりであまり大差がない。内装は入ってみないことには何とも言えないが、
“学び舎”という大看板を掲げる以上、年頃の女子を満足させるような物は、最低限に留めていると思ってまず間違いないだろう。
共用のシャワー室や、仮眠に使えそうなソファなりを周辺で探してみたものの、どうやら他人の家に上がりこまない限りは、
私の欲求を満たせそうもなかった。
非常事態であることと、記憶も所持品も何もないという身の軽さは、私を大胆にさせた。
数秒後には「家宅侵入が容易そうだ」という単純で物騒な理由から、新館を跨いだ旧館の方へと足を運んでいたが、
どちらを選んでも多分あまり違いはなかっただろう。寮内へは簡単に入ることができたが、個人の部屋のドアは当然のことながら
鍵が施されていたからだ。
仕方がなく裏手に回りこみ、ベランダに降り立った私は、持っていたハンカチを手に巻き、簡易錠のすぐ傍のガラスを叩き割る。
後ろめたさはあったが、今後の生活を考えると、安全かつ快適に過ごせる拠点は咽喉から手が出るほど欲しかった。
礼と謝罪の意味を込めて軽く頭を下げると、ガラスの割れ目に手を差し入れ、開錠して部屋へと入る。
カーテンを退けた先にあったのは・・・カラッポの空き部屋だった。
可愛らしいチェック柄のカーテンだけが、不自然に揺らいでいる。日に焼けた風もなく、住居人がどこかへ引越す際に、
取り残されて間もないのだろうとはじめは思った。
『空クジ』を引いたのだとはじめは失笑してみたけれど、何かがおかしい。
誰も使用していない普通の空き部屋なら、チリの一つくらい堆積してもいいものだが、新築か改装したばかりのマンションのように
床にはチリどころか傷一つない。学生寮という、下から数えた方が早いグレードの物件とは思えない高品質ぶりである。
これと似た違和感はさっき体験した。
校舎での出来事が脳裏を掠め、もしやと思い、二件、三件と同様の手口で犯行を重ねたが、どこも似たようなものだ。
外から見えるカーテン部分だけが取り繕われ、内部がスカスカなところなど、職員室の机や書庫棚のファイルとまるで変わらない。
求めていたふかふかのベッドも無ければ、替えの服を拝借しようとしていた箪笥はおろか、下着一枚見当たらない。
バスルームに向かい、シャワーの水も出ないというトドメを受けて、私は黙って浴槽の縁に腰掛ける。
本当に・・・・・・この世界は何もないんだなとつくづく思い知らされる。
あの教室だけが例外的な空間で、他には何もないハリボテなのだと理解するべきなのだろうか・・・。
右手が痛んだ。開錠する時にガラスで切ったようで、見ると小指の根元から4cmほどパックリ割れていた。
そこから血がとめどなく溢れ出る。スカートに落ちた血は黒く染まり、徐々に大きな沁みを広げていく。
今更到来した痛みに顔をしかめながら、ハンカチで止血して一息つくと、不意に零れそうになった涙を拭う。
ここ居ても仕方がない。多少寝苦しいだろうが、あの教室で寝る他はあるまいと観念した私は、中から玄関の鍵を開けて
のろのろと這い出した。ボロボロになった制服を見つめ、ベッドとシャワーへの未練が捨てきれない私は、出口付近の廊下を
グズグズとしていたが、寮の部屋割り名簿を目にすると、ある可能性に「もしや」と手に取った。
来ヶ谷唯湖 104号室
教室へ戻る事は決意していたが、絶望を抱くか、わずかでも希望を抱いて戻るかでは雲泥の差があった。
来ヶ谷の机にあった鍵束を引っ掴むと、すぐさま女子寮の旧館へと舞い戻り、私は来ヶ谷唯湖の部屋の前に立つ。
鍵の一つを鍵穴に差し入れながら、期待と不安でごちゃ混ぜになった感情が頭の中を駆け巡る。『どうせさっきの部屋と同じだ』
という嘲笑と、『あの教室が例外なら、そのクラスの彼女の部屋にも例外が及んでいる可能性は否定できない』という葛藤が、
カチャリという開錠音で胡散霧消する。
早くなる鼓動と、震える手を制するように深呼吸一つして、私はノブを回す。
開けた先の部屋は・・・簡素ながら、人間の匂いの沁みた落ち着く部屋だった。
蛍光が灯り、水道を捻れば水が出た。ごくごく当たり前のことが得られただけなのに、私の心は浮かれていた。
他人の部屋を使用することに躊躇いはあったが、来ヶ谷唯湖はもとより、人間はもうここには私一人しか居まいという達観があった。
なら有用に使わせてもらうまでだ。
服を脱ぎ捨てると待ち望んだシャワーを浴びて、来ヶ谷唯湖の所有していた服を一揃い拝借する。ジーンズにシャツ一枚という格好だが、
部屋着としてなら文句はない。測ったように丈がピッタリなのは嬉しい誤算である。
軽い家捜しを行ってみたところ、台所の戸棚からはカップメンを含むレトルト系の食料一週間分ほどを見つけることができた。
これで当面は飢餓の心配なさそうだと胸を撫で下ろす。
クローゼットの奥からは救急箱を探し当てた。中を開けてガーゼと包帯を見つけると、ぞんざいに応急処置だけしていた
右手の切り傷に巻いていく。血でぱりぱりに乾いたハンカチをそろりと剥がすと出血したが思ったより傷は浅いようだ。
手を軽く動かしてみる。多少の突っ張り感はあっが、普通に生活する分には問題ない。
ベッドに横になり、ようやくの安楽を堪能すると、枕に顔を埋めながら、私は来ヶ谷唯湖の部屋に視線を転がしていた。
目の前には、暇つぶし用の雑誌が何冊か置いてある。一番新しい表紙にはポップ調に設えられた2007年の7月号というロゴ。
今日が6月20日で、雑誌が7月号だとするなら大体の辻褄は合いそうだと一人納得する。
恐らく来ヶ谷唯湖や多くの人間は6月まではここに居たのだ。日常的な生活をしていたが、何らかの予期せぬ自体が起り、
私だけがここに残されてしまった―――ということなのだろう。
一応の結論は見えても不可解な点は多い。
何故この学校が孤立してしまったのか。そして電気は校舎にも供給されていたが、水道やガスのすべてが備わっているのは
今のところここだけだということ。例外的な空間があの教室と、その教室の生徒であった来ヶ谷唯湖に繋がっているというのなら、
あの教室の生徒を一通り調べてみれば何か分かるかもしれない。
そうすれば、私が誰であるのかというのも自ずと見えてくるのだろうか?
私はここから抜け出すことが出来るのだろうか?
回答を得るまでに私が生きていられるのだろうかという暗雲とした疑問を振り払い、疲労で朦朧とする意識に私は暗幕を下ろした。
今も降り続ける光の欠片―――
それの意味を、私はまだ知らない。
* * * * * * * * * *
初めに見たものは虚空を舞う幾千もの光だった。
風に乗って舞う綺羅星の粒は、一面を銀世界に染め上げている。雪か何かだと誤解していたが、晩春を思わせる気候と
樹木に息吹く緑の青さが、論理の矛盾を突きつけていた。
落ちてきたその欠片を私は掌で受け止める。
冷たくもなければ、暖かくもない。肌に触れると瞬く間に無に帰した。
「これは何なのだ?」という疑問の答えは出ないまま、広い敷地にポツリと佇んでいた私は小さく息を吹き返して、何度目かの溜息を吐く。
今まで何をしていたのだろうと思い起こそうとして、以前の記憶が綺麗に白紙になっていることに少なからず動揺したのはつい先ほどのことだ。
日時も、場所も、自分の名前さえも忘れた境遇において、唯一分かっているのは『私が女である』というどうでも良いことだけだったというのも
情けない。
身につけている制服からどこかの女学生であり、そしてその私が通っているところが、私の眼前にそびえる洒脱な校舎であることだけは
なんとなく察することができた。
梅雨時を思わせる薄暗い雲の暗幕は、昼とも夕刻ともとれそうで、おおよその時刻を推測することすら叶わないが、早朝や深夜でないこと
だけはたしかな筈だった。
なのに、どうしてあたりはこんなにも静かで、私以外誰一人としていないのだろう。
無音過ぎて耳が痛い。
ここで立っていても意味がないことだけは確かだ。手始めにポケットに手を入れて所持品の確認をする。
何かの手がかりになりそうな物があればと期待したのだが、生徒手帳は元より、記憶に繋がりそうな物は何一つとしてない。
おとなしめの柄のハンカチとポケットティッシュが一つずつ。 財布は持ち歩かないタイプの人間なのか、平日の学校では
充分と思われる小銭が数枚あるだけだ。
現実はこんなものだと肩をすくめると私は一直線に校舎へ向かう。
「おい、誰かいないのか!?」
体育館と思しきアーチ状の建造物を手近の窓から覗いてまわるが、中はガランドウで、ワックスで綺麗に磨かれた床が鈍く光る他は、
これといって目を惹くものはなさそうだ。
そのまま歩を進めると中庭と思しき場所に出た。渡り廊下を挟んで校舎が二つある造りで、こうして間近で見ると意外と大きい。
どちらから探索するか一瞬迷うが、何とはなしに右の棟に足を向ける。
「失礼する」
一階の『職員室』と表札の掛かった部屋はやはり無人だった。
生徒数十人を抱えるであろう担任がここにひとところ集まり、翌日の授業準備や、成績を付けたり、雑務をこなす場にしては異質すぎるほどに
整頓されている。遠慮がちに適当な机の引き出しを開けてみるが中はカラッポだ。そのまま下段の二つも調べてみたが何もない。
書庫棚に整然と詰め込まれたファイルの背表紙は何のラベリングも無く、もしやと思い一冊取り出してパラパラとめくってみた。
「・・・記憶喪失で右往左往している乙女に対して、この冗談はちょっとキツイな」
真っ白のページだけが最後まで続いていた。
次のファイルも、次のファイルも・・・・・・・・・・全部が白紙だった。
窓の外は相変らず光の粒子が淡い燐光を発している。
まるで世界の終わりのように―――
職員室を飛び出し、私は走った。
階段を駆け上がり、二階、三階、四階と顔だけ覗かせたが、廊下に誰もいないことが分かると上を目指す。
屋上に続く階段の終着点にたどり着く頃には、軽く上気してうっすらと汗をかいていたが、私は気にも留めず外へ続くドアに手をかける。
手製で『屋上 立ち入り禁止』と書かれた紙のぶら下がる謹製のドアは重く、ノブを回してみると鍵が掛かっている。
蹴り上げてみるがビクともしない。
舌打ちして周囲を見回すと、目線の少し上に人が一人、何とか潜れそうな窓が見えた。
一瞬躊躇したが、それを蹴破る。破片を取り除き、注意して屋上に降り立つと私は下界を見下ろした。
確かめたいことがあったのだ。
現実ではありえない現実と、体験した不可解な状況。この閉鎖した世界と、私の混乱した思考を打破する何かがあると思ってここに来た。
来たはずなのだ。
それなのに・・・・・・・・
そんなはずはない、あるはずがないと、駄々っ子のように私はイヤイヤと首を振る。
乱れた髪が顔に張り付いて、身体が小さく戦慄いた。
学校の敷地より先の物がことごとく消失している。
校門より先は黒い空間が蠢いており、その中でこの学校だけが孤島のように浮いている。端の方は目を凝らすと、少しずつだが
削れているようだった。ぽろぽろと零れて、闇が世界を侵食していた。
「・・・・・・・・・馬鹿馬鹿しい」
鼻で笑おうとして私の顔は歪んだ。夢か何かだと信じたかったが、汗で張り付いた服の肌触りと、血の気の引いた我が身がどこかで
何かを悟っていた。
光が積もっていく。
どんどん、どんどん。すべてを覆い尽くすように・・・。
緊張した肺に酸素を取り込む行為は予想以上に難航した。自らを叱咤するように一度頬を叩き、挫けそうな気持ちに喝を込める。
異常な事態に巻き込まれている事は理解したが、頭と気持ちが未だ混乱していた。
どこか落ち着ける場所で、気持ちを整理する時間が欲しい。今の私には、この屋上の光景は刺激が強すぎた。
それに・・・・光の粒が私に触れる都度、この学校同様に何かを削られているような喪失感を味わった。
出来れば外に居たくない。
重い足取りで再び校舎に戻る。一時間にも満たない短時間で起った訳の分からない出来事の数々に、私の頭は大分疲れていた。
下りる段数を数える気も起きず、適当な階の適当な教室に入ると、目に付いた机の椅子に腰掛けた。
「さて、どうしたものか」
天上を見上げて私は頭に腕を載せた。独り言を呟いてみたものの、それに対する解はおろか、芥子粒ほどの情報すら仕入れていない私に、
いったいなにが弾き出せるというのだろうかと苦笑する。
いっそこのまま眠ってしまえば、すべてが解決しているのではないかという淡い期待が湧いてしまう。少々気が滅入っているし、
ここで寝てしまうことへの抵抗はさほどない。毛布くらいは欲しいものだがと、あるはずもない物品を求めて教室に視線を彷徨わせて―――
私は腰を浮かせた。
あまりに当たり前すぎて、入った時は気にも留めていなかったが、この教室にはどこか人が時間を過ごした匂いとも言うべき煩雑さが窺えた。
わずかに傾いだ机。生徒が立ち上がって、そのまま在らぬ方向を向いた椅子。消してはいるものの、数式や文章痕の残る黒板と、
その下のチョーク受けに積もった色とりどりの粉粒。ホコリっぽい空気。
後ろの生徒ロッカーに残された物は学業用の書物や、何故か一角を占める筋トレグッズの山、不要と思われる携帯ストラップや漫画、
雑誌、その他諸々。
不思議に思い、席を立ってこの階の教室を一通り見て廻ったが、他の教室は職員室と同じだった。機能的に画一化されて、
人の匂いすらしない無菌室のよう。
再び例の教室に戻った私は背中越しに扉を閉める。
理由は不明だが、この一角だけが例外的な措置を施されていることは確かなようだった。
過剰な期待をすると失望した時の反動が大きいと分かっていても、気持ちはとても正直だ。
高まる鼓動を抑えて、まずは教壇の机にぽんっと無造作に置かれた座席表を手に取った。
見知った名前があれば、そいつのロッカーと机にある物品を物色して、芋蔓式に情報を取得しようという心積もりだったが、
無くなった私の記憶を呼び覚ますような名前はザッと見た限りではなさそうだ。
あの筋トレグッズの所有者が、井ノ原真人という生徒のものである事は了解できたが、無駄な知識を増やしてしまったようで妙に腹立たしい。
能美クドリャフカという生徒にも目が行ったが、単に名前が珍しかったからだろう。
原口雄介、三野瀬仲百合、棗鈴、井上和也、直枝理樹、佐々口洋平、小町洋子、神北小毬・・・・・・・・・・
そうそう巧くいくものではない事は予想していたが、現実の壁というヤツは、ほんの少しも私の期待を叶えてはくれないらしい。
この教室が私と何か関連があると仮定した上での行為も、どうやら無駄に終わったようだ。何人かの机やロッカーを覗き込んだものの、
どれもこれも先ほどのような輝きを失い、私にはただのガラクタの山のようにしか見えない。
疲れた・・・・・・・。
失望は思ったよりも私の気力を萎えさせた。
倦怠感と虚脱感が、私の身体に重く圧し掛かる。
やはりここで寝てしまおうかと思ったが、どうやら私も一端の『女の子』らしい。ベッドと熱いシャワーが恋しかった。
汗でべとついた体と、ごわついた髪を何とかしたいという欲求は、こんな状況においてもしっかりとあるようで、なんだか可笑しくなる。
そういえば、この校舎の正面口玄関に学校の見取り図が掲載されていたことを思い出す。たしか隣の校舎を越えたところに女子寮があった。
そこまで行けばそれらしい設備もあるだろう。
教室を出る前に、ふと気になって座席表を見直した。
無意識に座った座席の生徒に、ほんの少しだが興味があった。
来ヶ谷 唯湖
静謐の湖面を思わせるその名前は、凛として美しいけれど、どこか寂しい。
彼女の私品を物色したが、あまり持ち込むタイプの人間ではないようで、目に付く物はさほどなかった。
気になったのは、鍵の束が放置されていたことと、当人のものと思われる携帯電話が無造作に机の中に置いてあったこと。
メール履歴を盗み見たが、友人と面白おかしくやっていたのだなくらいしか窺えない。後半の履歴の多くは恋文のようだった。
最初の数行は読んでみたものの、他人のプライバシーを侵害している背徳感に私は目を逸らす。
外部に繋がる可能性を期待して、警察と消防署に掛けてみたが不通のようだった。メモリから任意の番号を引き出して掛けてみるが、
・・・・やはり不通である。
待機画面に戻すと、ディスプレイには2007年6月20日の文字。
どうやらそれが今日の日付らしい。
鍵の束の方は、自宅のものと思われるものを含めて全部で3つ。ということは、彼女が自宅に帰る前に突発的な何かが起って、
今のような事象が継続しているのではないかという可能性が想像できたが、それが正しかったとしても今の私には何の解決も提示してはくれない。
「・・・来ヶ谷唯湖女史。キミは私を知っていたのだろうか。知っていたらならば教えて欲しかったな。記憶を失う前の私は、
一体どんな人間だったのかを・・・・」
* * * * * * * * * *
女子寮は新館と旧館があるようだった。
ここもどこか無機質で、人の気配がないのも相変らずだ。
外から見た経年劣化の具合の程は、どちらも似たり寄ったりであまり大差がない。内装は入ってみないことには何とも言えないが、
“学び舎”という大看板を掲げる以上、年頃の女子を満足させるような物は、最低限に留めていると思ってまず間違いないだろう。
共用のシャワー室や、仮眠に使えそうなソファなりを周辺で探してみたものの、どうやら他人の家に上がりこまない限りは、
私の欲求を満たせそうもなかった。
非常事態であることと、記憶も所持品も何もないという身の軽さは、私を大胆にさせた。
数秒後には「家宅侵入が容易そうだ」という単純で物騒な理由から、新館を跨いだ旧館の方へと足を運んでいたが、
どちらを選んでも多分あまり違いはなかっただろう。寮内へは簡単に入ることができたが、個人の部屋のドアは当然のことながら
鍵が施されていたからだ。
仕方がなく裏手に回りこみ、ベランダに降り立った私は、持っていたハンカチを手に巻き、簡易錠のすぐ傍のガラスを叩き割る。
後ろめたさはあったが、今後の生活を考えると、安全かつ快適に過ごせる拠点は咽喉から手が出るほど欲しかった。
礼と謝罪の意味を込めて軽く頭を下げると、ガラスの割れ目に手を差し入れ、開錠して部屋へと入る。
カーテンを退けた先にあったのは・・・カラッポの空き部屋だった。
可愛らしいチェック柄のカーテンだけが、不自然に揺らいでいる。日に焼けた風もなく、住居人がどこかへ引越す際に、
取り残されて間もないのだろうとはじめは思った。
『空クジ』を引いたのだとはじめは失笑してみたけれど、何かがおかしい。
誰も使用していない普通の空き部屋なら、チリの一つくらい堆積してもいいものだが、新築か改装したばかりのマンションのように
床にはチリどころか傷一つない。学生寮という、下から数えた方が早いグレードの物件とは思えない高品質ぶりである。
これと似た違和感はさっき体験した。
校舎での出来事が脳裏を掠め、もしやと思い、二件、三件と同様の手口で犯行を重ねたが、どこも似たようなものだ。
外から見えるカーテン部分だけが取り繕われ、内部がスカスカなところなど、職員室の机や書庫棚のファイルとまるで変わらない。
求めていたふかふかのベッドも無ければ、替えの服を拝借しようとしていた箪笥はおろか、下着一枚見当たらない。
バスルームに向かい、シャワーの水も出ないというトドメを受けて、私は黙って浴槽の縁に腰掛ける。
本当に・・・・・・この世界は何もないんだなとつくづく思い知らされる。
あの教室だけが例外的な空間で、他には何もないハリボテなのだと理解するべきなのだろうか・・・。
右手が痛んだ。開錠する時にガラスで切ったようで、見ると小指の根元から4cmほどパックリ割れていた。
そこから血がとめどなく溢れ出る。スカートに落ちた血は黒く染まり、徐々に大きな沁みを広げていく。
今更到来した痛みに顔をしかめながら、ハンカチで止血して一息つくと、不意に零れそうになった涙を拭う。
ここ居ても仕方がない。多少寝苦しいだろうが、あの教室で寝る他はあるまいと観念した私は、中から玄関の鍵を開けて
のろのろと這い出した。ボロボロになった制服を見つめ、ベッドとシャワーへの未練が捨てきれない私は、出口付近の廊下を
グズグズとしていたが、寮の部屋割り名簿を目にすると、ある可能性に「もしや」と手に取った。
来ヶ谷唯湖 104号室
教室へ戻る事は決意していたが、絶望を抱くか、わずかでも希望を抱いて戻るかでは雲泥の差があった。
来ヶ谷の机にあった鍵束を引っ掴むと、すぐさま女子寮の旧館へと舞い戻り、私は来ヶ谷唯湖の部屋の前に立つ。
鍵の一つを鍵穴に差し入れながら、期待と不安でごちゃ混ぜになった感情が頭の中を駆け巡る。『どうせさっきの部屋と同じだ』
という嘲笑と、『あの教室が例外なら、そのクラスの彼女の部屋にも例外が及んでいる可能性は否定できない』という葛藤が、
カチャリという開錠音で胡散霧消する。
早くなる鼓動と、震える手を制するように深呼吸一つして、私はノブを回す。
開けた先の部屋は・・・簡素ながら、人間の匂いの沁みた落ち着く部屋だった。
蛍光が灯り、水道を捻れば水が出た。ごくごく当たり前のことが得られただけなのに、私の心は浮かれていた。
他人の部屋を使用することに躊躇いはあったが、来ヶ谷唯湖はもとより、人間はもうここには私一人しか居まいという達観があった。
なら有用に使わせてもらうまでだ。
服を脱ぎ捨てると待ち望んだシャワーを浴びて、来ヶ谷唯湖の所有していた服を一揃い拝借する。ジーンズにシャツ一枚という格好だが、
部屋着としてなら文句はない。測ったように丈がピッタリなのは嬉しい誤算である。
軽い家捜しを行ってみたところ、台所の戸棚からはカップメンを含むレトルト系の食料一週間分ほどを見つけることができた。
これで当面は飢餓の心配なさそうだと胸を撫で下ろす。
クローゼットの奥からは救急箱を探し当てた。中を開けてガーゼと包帯を見つけると、ぞんざいに応急処置だけしていた
右手の切り傷に巻いていく。血でぱりぱりに乾いたハンカチをそろりと剥がすと出血したが思ったより傷は浅いようだ。
手を軽く動かしてみる。多少の突っ張り感はあっが、普通に生活する分には問題ない。
ベッドに横になり、ようやくの安楽を堪能すると、枕に顔を埋めながら、私は来ヶ谷唯湖の部屋に視線を転がしていた。
目の前には、暇つぶし用の雑誌が何冊か置いてある。一番新しい表紙にはポップ調に設えられた2007年の7月号というロゴ。
今日が6月20日で、雑誌が7月号だとするなら大体の辻褄は合いそうだと一人納得する。
恐らく来ヶ谷唯湖や多くの人間は6月まではここに居たのだ。日常的な生活をしていたが、何らかの予期せぬ自体が起り、
私だけがここに残されてしまった―――ということなのだろう。
一応の結論は見えても不可解な点は多い。
何故この学校が孤立してしまったのか。そして電気は校舎にも供給されていたが、水道やガスのすべてが備わっているのは
今のところここだけだということ。例外的な空間があの教室と、その教室の生徒であった来ヶ谷唯湖に繋がっているというのなら、
あの教室の生徒を一通り調べてみれば何か分かるかもしれない。
そうすれば、私が誰であるのかというのも自ずと見えてくるのだろうか?
私はここから抜け出すことが出来るのだろうか?
回答を得るまでに私が生きていられるのだろうかという暗雲とした疑問を振り払い、疲労で朦朧とする意識に私は暗幕を下ろした。
今も降り続ける光の欠片―――
それの意味を、私はまだ知らない。
* * * * * * * * * *
 それからというもの、来ヶ谷唯湖の寮部屋を拠点に、私の校内の探索は毎日のように行われた。
初めに確認した『来ヶ谷唯湖』という女性徒。彼女の席に隣接する生徒の寮部屋から一つずつ潰していくという
地味な作業からのスタートだったが、目的意識があるだけで孤独という寂しさは何とか紛らわすことができていた。
ベランダのガラスを壊すには、教室にあったダンベルセットの中から、長さ30cmほどの鉄棒を失敬して使わせてもらっている。
鉄棒を振り回して無人の学校を徘徊する少女―――
想像してみるとただの不良少女のようだが、やっている事はその通りなので言い訳も出来ないなと無理に笑う。
まだ半分ほどしか“作業”は進んでいない。今のところ来ヶ谷唯湖と同様に、例外的に人間の匂いが残存している寮部屋は、
神北小毬、西園美魚、棗鈴、能美クドリャフカの4人ということを確認できていたが、来ヶ谷唯湖ほど完全に部屋が残っているところは
一つもなかった。
神北小毬の部屋は、半分以上が虚無の浸食を受けたような惨状だった。あるラインを境にして、いかにも女の子らしい部屋が
飾り立てられているのに、片側は空き部屋のような有様。西園の部屋は表層の作りはちゃんとしているのに、机や本棚を漁ると
職員室と同じでカラッポか、白紙の束を束ねた装丁の小説が並んでいた。
能美や棗鈴の部屋も似たようなものだ。
進捗は斯様に足踏み状態を維持したままだが、幸か不幸か、この作業の最中、私は“ジョーカー”を拾っていた。
ババ抜きの『ハズレ』か、ポーカーで力を発揮する『当たり』かはまだ見当が付かないが、何らかのヒントを提示している事は確かだった。
来ヶ谷唯湖を含めた例の四人が、同じ写真を所有していたのだ。
多分、それぞれが最も大切に保管できる場所、見栄えの良い最良の場所を選ぶように、あるものは仕舞われ、あるものは飾られていた。
何かの記念なのか、10人の男女が和気藹々と写っている。裏には『リトルバスターズ』と記載され、部活か何かのメンバーで
あることは容易に想像できた。
写真には私も映っていた。
巨漢の男と、いかにも清楚な印象の女性に上下を挟まれる形で、可愛らしく顔だけを覗かせて微笑んでいる。
まともな写真はこの世界ではそれ一枚きり。アルバムを時には見かけることもあったが、収められた写真のすべてが真っ白の紙切れと
化していた。何故かは分からないが、『何か』がこの写真にある―――ということを如実に物語っている。
彼らがどんな連中なのかはこの写真だけでは察することができないが、少なくとも私は幸せだったのだろう。
こんな表情で笑い合える友人が居たのかと思うと、我が事ながら羨ましいと今の自分を省みて、つくづく思い知らされる。
一日の終わりになると、私は毛布に包まりながら、来ヶ谷の寮にあるその写真を眺めては物思いに耽るようになっていた。
どれかは分からないが、多分この中に来ヶ谷唯湖も居るはずだった。
それはつまり、来ヶ谷唯湖と私は面識があったということになる。
私達は、一体どんな話をしたのだろう・・・?
* * * * * * * * * *
何日かが経過した。
昨日、女子寮を一通り終えることができた私は、その日ようやく男子寮に手を付けていた。
座席表の男女を調べる程度なら二、三日で事足りるだろうと当初は楽観していたが、物事には常に山あり谷ありだと、
私は改めて思い知らされる。
全員が地上階であれば苦労などしないのだが、それが上階となると話は別だ。基本的に鍵の掛かった寮部屋への侵入は、
ベランダをつたって二階、三階へよじ登るという行程が必要となる。右手の傷が癒えてない私にとって、この作業はかなり堪えた。
当然、正攻法で正面突破を試みたこともあったが、力任せの破壊や、針金を曲げての鍵の開錠など、体力と時間の浪費だと早々に
悟って以来、専ら壁登りが主流である。
寮部屋がカラッポであれば一瞥して戻れば良いだけの話だが、部屋の内装が保存されていた場合、一通り調べるという作業が
これに加算される。このときほど人の所有する物品の多さに嫌気がさすことはない。一部屋だけで長いときでは半日以上を費やすのだから、
調査は女子寮だけで相当の日数を消費していた。
今回の男子寮の探索で、調べていた生徒が初回から三階であると知ったときの私の気分が如何ほどであったかは推して知るべし―――。
後に回そうかとも思ったが、どうせ、いつかはやらなければならないノルマである。やるなら早めの方がいいと覚悟を決めて、
三階に住居を構える他の二名の部屋も、まとめて片付けたのが数分前のことだ。
先日失敬した水筒から、水が咽喉を伝うのも構わずごくごくと飲み干して、私は息を吐く。作業時には当たり前となって久しい
ジャージの袖で汗を拭うと、大した収穫もなく無駄骨に終わったことを、勤めて忘れてしまおうと次の作業に取り掛かった。
手際は慣れたものだ。傍に置いたバッグから寮の玄関口に張られていた部屋割り名簿と、教室にあった座席表を見比べては、
先ほどの部屋の留意点を書き込んでいく。
その姿は一介の女学生とは思えないほど凛々しいけれど、肌に載った疲労の色は隠しようがない。
孤島に一人だけ取り残された人間がはじめに飢えるのは、人との触れ合いだといわれている。寮部屋を探索する目的が、
その意味合いを変化させつつあるのもそこに原因があるのだろう。例の教室と、生徒たちの関連を解き明かすことよりも、
誰か他に人が居ないかを主眼に寮部屋を放浪している自分に気付いたのは、つい最近のことだ。
記憶喪失による精神的な不安と、「私は誰であるか」という強迫観念。
閉塞した世界と支えのない孤独感が、その気持ちを更に助長していたのだろうが、焦燥は強くなるというのに得られる成果は微々たるものだ。
ベランダをつたって上り下りする私の寮の探索と比べ、日常そのものは平坦で起伏がない。同じ日を何度も繰り返しているような、
奇妙な既知感に囚われてしまう。
そのためか、私がこんな目に合って、いったい幾日経過したのか・・・実を言うと、もうほとんど憶えていない。
降り注ぐ光のカケラは止む事を知らず、同じ風景と、同じ日常の繰り返しに、当の昔に私の心根は折れていたのかもしれない。
感情の限り叫んで、人を求めたこともあった。
「何でこんな目に・・・」と、一日中来ヶ谷唯湖の部屋から出なかったこともある。
私はもう知っている。ここには本当に、私一人しかいないという事を。
けれども、人を探さずにはいられない。暇を見つけては校舎の中も探してはいたが、確率的に誰かが居るとしたら寮部屋以外に
考えられなかった。
不毛と知っていながら、こんなことを続けている私は馬鹿なのだろうか。
それとも、どこかで狂ってしまったのだろうか。
窓を壊しても、部屋をめちゃめちゃに荒らしても、何事もなかったかように翌日にはすべてが元に戻っている事象を目撃してからと
いうもの、どこかで私の心のバランスは崩れ始めていた。
負担ばかりかけていた左腕は小刻みに震えていた。
それが伝染して、震えが身体を覆っていく。
誰でも良い。
ただ・・・誰かと逢って話しをしたかった。
バラバラに壊れそうな部品を繋ぎ止めている私の糸は、今にも切れてしまいそうだ。
それでも平静を装い、次の目標となる男子生徒の部屋を探していたところ、ある名前で目が止まる。
棗恭介・皆川早瀬 312号室
どこかで見たことのある名前だった。
私は最近の記憶を掘り起こそうと、感傷的になっていた気持ちを切り替える。
棗恭介・・・・。棗―――そう、棗鈴だ。
珍しい苗字からも、棗鈴と血が繋がっていると推測するのもあながち的外れではあるまい。調べてみても損はないと判断した私は、
とりあえずの目標を見つけることができて、ほんの少しだけいつもの平静さを取り戻す。
こういう収穫のあるときはいい。思考を循環させている間だけ、嫌なことから目を背けていられるから。
それにしても、例の教室の生徒にしか目が廻っていなかった自分が憎らしかった。
部屋番号からして三階だろう。軽く眩暈を覚えるが、そこはグッと堪えて名簿をバッグに仕舞い、小脇に抱えると、一応、
部屋のドアが開いていないかを調べに階段を上って三階へ向かう。
一度として開錠された状態の寮部屋というものを拝んだ事はないのだが、ベランダをよじ登るという重労働を回避する可能性が少しでも
あるのだ。この階段を上る程度の労力で済むのなら、確認してみる価値はある。
疲弊した身体に鞭打ちながら、私は一段、また一段と足を運ぶ。
それにしても、男子寮の名簿は見ていたのだが・・・棗恭介を見過ごしていたことが、どこか腑に落ちなかった。まぁ、棗鈴の
『家宅捜査』を行うまでは、あまり気にも留めていなかった苗字なのだから、見過ごしていたのも当然といえば当然なのかもしれないが・・・・。
例の写真には確かに兄妹らしい二人の姿が写っていたと思う。いかにもやんちゃそうな男と、どこか困った表情のポニーテールの少女。
棗鈴と棗恭介があの二人だとするなら、私と能美クドリャフカの合わせた四人が、あの写真の中で顔と名前が一致したことになる。
女生徒の来ヶ谷唯湖、神北小毬、西園美魚で女子の数は合うから、残った男子生徒3人を見つけることが今後の課題であろう。
これがすべて終わった先にある予感を、私は勤めて見ないようにしていた。これだけの時間と労力を費やしていながら、得られたものは
友人と思われる9人の存在を映した写真一枚きり。すべてが徒労に終わるであろうことをどこかで悟っていても、止めることなど私に
できるはずもない。
そこで足を留めてしまったら、私は『現実』を見つめなければいけなくなる。
過酷な現実を目の前にすれば、私の心はきっと死んでしまう。
だから私は、あの写真に依存する。
一日の終わりになると、あの中の生徒達との日常を空想しては、現実から飛翔して、もう二度とこの世界へ舞い降りてこないようにと
切に願って布団を被る。漂流したこの世界の方が間違いで、きっと夢か何なのだと自分に言い聞かせて・・・・。
どんなに強くあろうとしたって、私はちっぽけな一人の少女でしかない。力が強かろうが、どんなに賢かろうが、ひとりきりの自分を
満たす糧にはなりはしない。
こんな現実と今こうして付き合っているのだ。
少しくらい夢を見たっていいじゃないか・・・
舞い落ちる光の粒子は、とうとう寮の内部にも浸水していた。
どこから落ちてくるのか、ひらひら、ひらひらと私の目先を過ぎっては、小さな夢を灯しては消えていく。
空ろに沈む私の瞳は、やがてカケラの残骸に吸い寄せられる。
リトルバスターズの面子と、私の間にあった関係はどのようなものだったのだろうかと想いを馳せていると、うつらうつらと舟を漕ぐように、
気付けば私の意識はどこか遠くに流されていた。
私を苛めていた孤独と疲労が、とうとうピークに達してしまったのかもしれない。「こうであったら良いな」という過去を妄想しては、
現実から目を背けようとする何かが、私の『何か』を断ち切ろうと首に手をかけていた。
私が笑っている夢
私がささやかな恋している夢
私が多くの仲間たちに囲まれて、日常の学校生活を過ごす夢
とても甘くて、魅惑的な夢だ。いつまでも続けばいい。あの写真の仲間達に囲まれて、どこまでもどこまでも、楽しく平穏な世界を
ぐるぐると、ぐるぐると・・・・・・・・。
死ぬまで妄想の世界で生き続けれると言うのなら、それは確かに幸せなことなのかもしれない。
ふうっと訪れる陶酔に身を委ね、静かに闇に落ちそうになる私の背中を、誰かがそっと抱きしめたような気がした。
―――そんな世界、僕は認めない・・・・!!―――
誰だったろう?
以前誰かに言われた言葉が木霊した。
華奢な体つきをしているくせに、人一倍健気で、誰よりも優しくて、強い人。
だから私は・・・。
私は・・・・・・・
「・・・どうしたのだろう・・・?」
数日に渡る強行軍で、肉体的にも精神的にも限界に達していたのだろう。階段の途中で崩れるように倒れていた私は、
夢心地の頭を振って起き上がる。
何かを思い出しかけていたような気がしたが、それももう、夢と共に曖昧なものとなっていた。
無理な体勢で倒れていた為か、節々が痛い。散らばった所持品を拾い集め、廊下の窓から外を見回すと、いつの間にか三階まで
来ていたようだ。夢遊病者じみたあんな状態で、よくここまで来たものだと呆れてしまう。
ふと横を見れば314号室は目と鼻の先だ。
この部屋にもやはりあの写真があるのだろうか・・・・。
錠が掛かっていることを覚悟して軽くノブをひねると、拍子抜けるほど簡単にドアが開く。息を呑み、私はゆっくりと中を窺った。
光の届かない深海のように、深い闇が部屋を支配していた。
目を凝らすと、うっすらとだが二段ベッドらしき輪郭や、勉強机、平積みされた数冊の雑誌が識別できる例外的な空間だ。
どうやら棗鈴の血縁者という仮定もあながち間違いではなさそうだ。
例外者の中では私が見つけた初の異性でもある。新たな発見があるかもしれないと期待に胸を膨らませるが、こう暗くては
作業に差し支えが出る。
手始めに遮光カーテンをなんとかしないと・・・
部屋に足を踏み入れた私のすぐ後ろで突如ドアが閉まった。
慌ててドアを振り返るが暗くて何も見えない。おおよその見当で延ばした私の腕は虚空を薙いだ。
「・・・・・来ヶ谷・・・か?・・・どうやってここに?」
男の声が響いた。
人間の声だ。
記憶を失った私にとっては、“生まれて初めて聞く”他人の声。
一人じゃないことの嬉しさが全身を駆け巡るが、男の言葉を反芻していくうちに、私はゆっくりとだが醒めていく感覚を憶えた。
繋がった先の『ソレ』と自分を照らし合わせて、何かが鮮明になっていく。記憶の奔流と、混濁した感情。
頭の中が割れそうに痛むのを堪えて、確定した私という個体の正式名称を口にする。
「私が・・・・・・・・・・来ヶ谷・・・唯湖なのか・・・・・・・・・」
じゃあ、例の教室で無意識に自分の机に座ったことは一つの必然だったのか?
鍵と携帯が放置されていたのは、記憶喪失前の私が置いていただけ?
じゃあ、あの例外的な空間は・・・・
嵌り続けるピースの数は膨大に膨れ上がる。
圧倒的な物量に堪えきれず膝を突き、それでも私は男の顔を見ようと闇に目を凝らす。
「お前は誰だ・・・・・棗恭介か?」
質問の意味を巧く把握できなかったのだろう。
しばらくの沈黙が終わると、男は意外そうな声を上げた。
「・・・・おいおい、まさか完全に記憶をなくしているのか? そんな状態でどうやってあの世界を持続させて―――いや、そうか・・・。
それで俺の部屋に繋がったというわけか。記憶喪失にでもならなければ、お前が好き好んで俺の部屋にくるはずもないし・・・・
整合性は確かに取れるが・・・・」
「・・・・・・何が言いたい!? なにを言っている!?」
一人納得する男に苛立ちを隠せない私は、奥へと進む。
部屋の隅に浮かぶシルエットが、もぞりと動いた。
「来ヶ谷。お前の世界はもう終わりを迎えている。そこにあるのはただの『残骸』だ。“こっち”と繋がったのは、綻びの隙間を
巧く掻い潜れたからだろうという仮定しか出来ないが・・・・恐らく、お前の世界が完全に終わりを迎える前兆だろう。
・・・今のお前に話しても理解できないだろうが、お前の願いにはそもそも無理があったんだよ。『永遠』を願ったところで
破綻が生じる事は分かっていたはずなのに・・・・どうしてお前はその世界を願ってしまったんだ・・・」
分からない。
彼が何を言わんとしているのか私には理解できない。
「他に、願うべきものがあっ・・・た・・・ろ・・・。両親・・・関係・・・の修・・・・・・・・・・の・・・・に・・・」
「待ってくれ! 聞こえない! この世界はまやかしなのか? どうすればここから出られる!?」
男の声が遠い。物理的距離は3mもないというのに、歩み寄る私と男との距離はいくら経っても縮まらなかった。
あと、少し・・・あと少しがもどかしい。
「・・・・な・・・おえ・・・・き・・・。・・・わ・・・す・・・・れ・・・」
手の先が男に届いたのは直後のことだ。布地と思し手触りを頼りに私は一気に男を引き寄せる。
聞きたい事は山ほどある。そして男はそれを答えれるだけの知識を持ち合わせているらしかった。まずは顔だ。
写真の男なら、リトルバスターズについても聞けるだろうしこちらとしては好都合だ。
私はカーテンを力任せに引き毟る。レールごと盛大に剥がれて、外光が闇を駆逐する。
そうして目の前にあったのは、襤褸と化した唯の布切れだ。
男はおろか、部屋の中に確かにあったはずの二段ベッドもなければ、男のもとへ向かう最中によけたはずの、ゴミや雑誌の山は
陰も形もなくなっている。
狐に抓まれた面持ちの私は、辺りを見回して更に呆然とする。
314号室だった部屋は廃墟と化していた。
天上や側壁は失われ、吹きさらしの空からは、光の飛礫が舞い込んでいた。
いや、314号室だけじゃない。隣も、その隣も・・・・男子寮はおろか、数十メートル先にある校舎、女子寮、体育館。
何から何までが廃墟一歩手前の零落ぶりを晒している。
この世界の終わりの前兆―――
男は確かにそういっていた。
それが・・・・これか?
漂流していた学校の敷地はとうとう闇に飲まれ、グランドの半分近くが削れてなくなっている。侵食速度は以前と比べ物にならないほど
速く、数時間もすれば、すべてがあの闇に覆われるだろう。ここでオメオメしてたら私も崩壊に巻き込まれる。
314号室前に転がっていたバッグを抱えて、私は寮部屋を後にした。
とにかくこの世界から抜け出す方法を探さなければいけない。
最後に男はなんと言った?
なお・・え・・・・・直枝・・・・・
どこかでそんな名前を見かけたような気がして、座席表と、寮の部屋割り表を私は取り出した。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なんだ・・・・・・これは・・・・?」
プリンターで印刷された紙面の文字は、数十年の時を経たように擦れていた。名前を確認しようにも、うっすらと見えるのは
罫線くらいのもの。私の座席の場所がどうにか判断できる程度の解像度で、誰かの名前を特定するなどできるはずもない。
ついさっきまで普通の紙であったものが、どうやったらこうまで劣化するというのだ。
せっかく、何かが見えはじめたというのに・・・・!
私は力任せに地面に叩きつける。その一撃が紙書類の寿命を終わらせた。
チリ屑と化した紙吹雪は上空を舞い、それは突然、光の粒子となって虚空へと還っていく。
唖然とする光景を目の当たりにして、私はようやく光のカケラの正体に気付くことができた。地面も、草木も、建物に至るまで・・・・。
降っていたと思っていた光の粒子は、この世界を構築していた物質そのものなのか。
作り物の世界。その残骸の中で彷徨っていたのがこの私・・・来ヶ谷唯湖だったと言うわけだ。じゃあ私も誰かに創造にされた
作り物なのだろうか?
可能な範囲で自分の身体を調べてみるが、光の粒子が私から漏れ出す気配はない。少しだけ安堵するが、状況は何も変わってなどいない。
何か・・・何かできることはないかと思考を巡らせる。
直枝という人物の手がかりは何もないといっていいが、ある程度の推測は可能だ。リトルバスターズのメンバーの一人とするならば、
あの教室のどこかにそいつの机があるかもしれない。運がよければ所持品を見つけ・・・・そして更に運がよければそこから脱出する
手段―――。
常識的に考えて、そんなご都合的な可能性はゼロだとは分かっている。
けれど、動かなければここで屍を曝すだけだと走り出す。
例の教室はまだ健在だった。隣接する教室が既に朽ちているというのに、ここだけ日常の息吹を保管している。
区切られた境界を潜るように、私は教室の中へと舞い戻っていた。
窓の外から見える世界の終わりを告げる光は、その数を何千、何万と増やして一面を真っ白に塗り潰している。
チラホラとその光に混じって、遠い彼方の風景が二重写しに霞んでいた。
季節は初夏だろうか。
暑い日ざしが差し込み、木々がその緑を深めている。
白く塗られたキャンパスの先には、私の見知らぬ世界があった。
この世界はもう崩れ始めているのだ。このままここで息を潜めていれば、もと居た場所へと帰ることができるのかもしれないという
誘惑が過ぎるが、私は大きく首を振る。
違う。
まだ帰れない。帰ってはいけないと本能が警告していた。
私は何かを忘れている。この世界に何かを置き忘れたままだ。
戻った瞬間それは消えてしまう。
それではダメ。
それではこの世界を願った・・・・・・・意味が・・・・
今・・・私は何を口走った?
あの男と出会ったことで、何かが・・・・忘れていた記憶の断片が、ここに来て私の中に生まれつつあるのだろうか。
かつては他人だと思っていた来ヶ谷唯湖。その席に私は座り、必死に何かを思い出そうと努力する。そう、私は何かを願ったのだ。
全てをかなぐり捨ててそれだけを願った。それだけあれば他はもういらないとさえ祈った自分の気持ち・・・・。
あったはずなのに・・・・
痛いくらいに拳を握る。
思い出せないことが自分の罪であるかのように髪をぐしゃぐしゃにすると、声にならない絶叫を上げて私は机を蹴り飛ばした。
愚か過ぎる。
願いをした本人が全てを忘れているというのに、その願いだけが一人歩きをして、こんな世界を未だに残し続けているという事実が。
この世界は、私に何かを教えようとしている。そうでなければ、こんなにも無残になった状態で存続し続ける意味がない。
それとも無意識に、私という主体がこの世界に今に至るまで何かを願い続けているのかどちらだろう。
ダメだ・・・考えても分からない。
力なくうな垂れる私の顔はとうとう下を向いた。
携帯電話があった。
来ヶ谷唯湖の・・・私の携帯電話が、机が蹴り飛ばされた拍子に転がっていた。
全身に鳥肌が立つ。
藁をも掴むように私はそれを手に取った。
そうだ。あったはずだ。メールで、私は誰かに宛てて恋文を送り続けていた。
確信する。私が思い出すべき事はそれ以外にありえない、と。
私はゆっくりとメール履歴のボタンを押した。
受信メールはありません
たった一文の報告に、私の思考は停止した。
そして、ただ可笑しくて笑い出す。
そんな馬鹿な。あるはずがない、何かの間違いだともう一度、履歴ボタンを押す。
受信メールはありません
・・・・・・ありえない。
ありえない。ありえない。ありえない。
消した記憶はない。机から落ちた程度でメモリが飛ぶとも思えない。
送信メールの履歴も調べてみるが、こちらもどういうわけか『送信メールはありません』という無機質な文面が羅列されている。
電話の着信履歴、リダイヤル、友人のメールアドレスや電話番号の全てが初期化されていた。
購入したての市販品のようなものに成り下がってしまったそれを取り落とし、ただ無言で私は首を振る。最後の希望が枯れ落ちてしまった。
それを合図に、守られていた教室、机、私品の多くから・・・・光が洪水となってあふれ出す。
手遅れだったのだというには、あまりにも『それ』は近くを通り過ぎていた。
私が・・・来ヶ谷唯湖が思い出すべきだった何かを連れて、世界は徐々に白に埋もれていく。
こんなことで終わるのか?
この程度で私は何かを失ってしまうのか?
いやだ、いやだ・・・・!
気力を揺り起こして立ち上がると、もう不要とは分かっていたが、何かを閉じ込めていた携帯を、“遺品”を手に取るように
大事に抱えて私は教室を抜けた。ドアを抜けると同時に、他の教室と同様の姿に聖域は崩れ落ち、置いてあった私のバッグも、
それの余波を受けて光となって消えた。
よろよろと立ち上がる私の手元に残ったのは携帯と、三つの鍵束。
記憶を保持していた頃の、来ヶ谷唯湖の遺留品とも言うべきそれが、私に与えられた唯一の活路だった。
鍵の一つは寮の部屋としても、残りの二つは私に何を示唆しているのだろう。
一つは寮の鍵と似た形状で、残りの一つは3cmほどの長さのチャチな造りをしている。
使用場所は皆目見当も付かないが、何かの役に立つかもしれない。ポケットに仕舞うと、渡り廊下を抜けて、私は対向側の校舎へと
移動する。闇の侵食は、程なく向かいの校舎を飲み込んだ。気付けば寮側に立っていたこの校舎しか残っていない。
廃校同然のここが、最後の砦というわけだ。
だが、まだ全てが終わったわけじゃないと私は自らを鼓舞する。
崩壊が始まって、全てのものが崩れ落ちているという事は、逆に考えればチャンスでもある。
寮や例の教室のある校舎は一通りの調査を行ったが、寮側にある校舎は優先順位が低かったこともあり、それほど調べたわけではないのだ。
仮にあの教室のように、例外的な空間が存在するのであれば、今のこの状況なら、記憶を喪失した私にでも重要性が視覚的に
把握することができる。要は崩壊していない場所や物を探せばいい。
見つけるのだ。この崩壊の跋扈した世界で、来ヶ谷唯湖の想いを保持した『何か』を。
今の今になって、ようやく私は疑問の氷解音を聞いていた。
答えは単純だったのだ。
この世界の影響を受けずに残存していた例外的な空間や物は、私と繋がっていた。
リトルバスターズの写真
その中で笑う友人達の部屋
私が通っていた教室
来ヶ谷唯湖である私の部屋
全部、全部意味があった。
無意味なものなんて一つもなかったのだ。
ガラクタと吐き捨てた、あの教室にあった物品も突き詰めていれば、きっと何かの役に立ったかもしれないのに。
一階の廊下をひた走っていた私は『それ』を見つけていた。
周囲と比較して充分綺麗なドア。影響を受けていない証拠だ。
「放送室」というネームが貼られているが、果たしてこんな場所に何かあるのだろうかと首を傾げてしまう。しかも、当然のように
施錠されたドアはビクともせず、崩壊を起していない代わりに、私をも締め出して盤石の鉄壁を誇っていた。
裏から何とかならないかと外に向かおうとしたが、玄関口で生じた鈍い音が、私の勇み足を押し留める。ぐらりと校舎が揺れたのは
その直後だ。
玄関左手の校舎下の地表がとうとう闇に食われたのだ。寄りかかる土台を失くした校舎は自重に負けて半壊した。
体勢を低くしていた私には幸いにも大した怪我はなかったが、振動でもんどりを打った拍子に足首を挫いていた。
震災の第一波が収まるのを確認して、ひょこひょこと足を引き摺りながら窓に向かうと、私は身を乗り出して外を窺う。
あたり一面は闇の海と化していた。
空には崩れ落ちた天蓋がぽっかりと開いている。それはもう空というよりも、きらきらと光る豪華なシャンデリアを叩き壊した
瞬間の映像だ。ぶちまけられた光の粒が闇の黒に映えて、思わず見惚れてしまうそうだ。
天も地も周囲の建造物も根こそぎ消滅している。
食べ残しはここだけというわけだ。
あまり考える時間もないというのに、この堅牢なドアを攻略する方法で、ろくな案が浮かばない。寮のベランダから侵入というような
アクロバットな小技はやりたくても、右手は痛むし、足首は痛い慢心創痍状態。
移動も無理、力技も無理ときてはさすがの私も手の打ちようがない。
「もうここまでかな・・・・」
ニヒルなタフガイなら、ここでタバコの一つでも燻らせるのだろうが、生憎と私の手元に、そんな物は・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
サイドポケットに手をやると金属特有の硬質な手触りがあった。
取り出してみると鍵の束。
一つは寮の鍵。
そして一つは同系の鍵。
まさかな、とは思いつつも、その鍵を錠に差し込むと見事に嵌り込む。
そのまま半時計方向に回すとカチリ―――という小気味いい音を立てて部屋は私を招きいれていた。
狭い部屋だ。
もともと放送だけを目的としているであろう部屋に、マイクやら面倒そうな設備がこれでもかと突っ込まれているのだから無理もない。
奥には電子ピアノらしきデカブツが鎮座しておりなかなかに壮観だ。
放送室に入ると同時、朝からずっと酷使し続けた身体はもう限界だった。倒れこむようにフローリングの床に身体を横たえると、
私はそのまま身動き一つ取れなくなる。
床の冷たさがほてった身体に心地いい。妙な達成感を憶えて、私はこの世界で初めて作り笑いじゃない、本当の微笑いを浮かべることが
できた。
ここが私の終着点。
そして、多分・・・記憶喪失以前の来ヶ谷唯湖が一番の想いを込めた場所。
記憶喪失以前の私がここに何を感じ、何を経験して、何をしていたのかは分からない。
分からないけれど、それはきっととても大切なことだったんだろう。
闇と光のカケラに飲みこまれもせずに、最後までここが残ったのも偶然じゃない。
“ここを中心にして作られた世界”だからこそ、最後に残ったのがここだったというだけなのだと思う。
それが分かっただけでも、私は満足だった。
胸に酸素を充填すると、やがて私は大きく息をつく。
一人の少女によって創られた世界は、とうとうその限界を迎えていた。
不完全で、不恰好だったカタチは歪み、『世界の中心』である放送室へと闇は進行する。
壁が光のカケラとなって消えていく。
床も、機材も、そして、私自身も・・・・
恐くはなかった。
徐々に埋没する足はその存在感を失い、やがて腿、腰、胸を覆い・・・
最後に私の顔はとぷりと沈んだ。
結局、直枝という人物だけがよく分からなかったなと、私は感慨深く呟いた。
男なのだろうとは薄々とは感じていたが、やはりそれが誰なのかを理解することができないまま、来ヶ谷唯湖である『私』が、
私ではなくなることが少しだけ心残りといえた。
混濁した意識の中で、私は奇妙な夢を見る。
私が誰かに恋をしているという夢。
それは叶わぬ恋であり、私自身も分かっている悲しい夢。
とても儚く悲しいけれど、分かっていても、やはり私は彼を好きになるしかなかったんだと諦めたように小さく頬笑う。
けれどそれは夢。
どんなに苦しくて、恋しくても、それは夢。
だから忘れてしまおう。
悲しかったことも嬉しかったことも、全部この夢に詰め込んで―――
あとがき
|ω・`)
うん、多分一番空気読めてない作品だと思います。
というわけでまずは一言言わせてください。
スンマセンでしたー!!!!!!orz
さて(ぉ
今回のSSは、ウチのブログの『二次創作考察小説』というSSの番外編的位置付けの作品だったりします。やれることなら来ヶ谷の
補完的な作品もやりたいなと思っていた自分にとって今回の来ヶ谷祭はまさに渡りに船ということで投稿させていただきましたm(_ _)m
基盤にあったのは来ヶ谷シナリオの終盤からラストへの件に至る間の補完を、自分なりに妄想して書いてみたいというだけの話
なんですけどね(笑
全て読んだ方は色々言いたいことがあるでしょうが、題にもあるようにこれはあくまでもこれはver.B。
初回プロットとして自分の頭の中にあったのは3つ。
三つとも途中までは共通なんですが、終盤からの展開が分岐する仕様となっております。
まず今回のバッドエンドルートのVer.B(バッド)
終盤で実は『私』が来ヶ谷唯湖じゃないという超展開をするVer.F(フェイク)
コイツに関してはまぁ、さすがにアレだよなぁと思ってプロット段階で破棄しましたが、もうひとつのバージョンは恐らく、
これが上がる頃には完成してウチのブログにうpられていると思われます。
来ヶ谷シナリオといったら二つのエンドが唯一あるヒロインですからね。
考察を書いたりと思い入れがあるので、このような実験をさせて頂きました。
OKしてくださった神主あんぱんさま
そして今回リトルバスターズの簡易メモで、マップを参照させていただいた神海さま。
挿絵を描いていただいたごすさまにこの場を借りて感謝をm(_ _)m
それからというもの、来ヶ谷唯湖の寮部屋を拠点に、私の校内の探索は毎日のように行われた。
初めに確認した『来ヶ谷唯湖』という女性徒。彼女の席に隣接する生徒の寮部屋から一つずつ潰していくという
地味な作業からのスタートだったが、目的意識があるだけで孤独という寂しさは何とか紛らわすことができていた。
ベランダのガラスを壊すには、教室にあったダンベルセットの中から、長さ30cmほどの鉄棒を失敬して使わせてもらっている。
鉄棒を振り回して無人の学校を徘徊する少女―――
想像してみるとただの不良少女のようだが、やっている事はその通りなので言い訳も出来ないなと無理に笑う。
まだ半分ほどしか“作業”は進んでいない。今のところ来ヶ谷唯湖と同様に、例外的に人間の匂いが残存している寮部屋は、
神北小毬、西園美魚、棗鈴、能美クドリャフカの4人ということを確認できていたが、来ヶ谷唯湖ほど完全に部屋が残っているところは
一つもなかった。
神北小毬の部屋は、半分以上が虚無の浸食を受けたような惨状だった。あるラインを境にして、いかにも女の子らしい部屋が
飾り立てられているのに、片側は空き部屋のような有様。西園の部屋は表層の作りはちゃんとしているのに、机や本棚を漁ると
職員室と同じでカラッポか、白紙の束を束ねた装丁の小説が並んでいた。
能美や棗鈴の部屋も似たようなものだ。
進捗は斯様に足踏み状態を維持したままだが、幸か不幸か、この作業の最中、私は“ジョーカー”を拾っていた。
ババ抜きの『ハズレ』か、ポーカーで力を発揮する『当たり』かはまだ見当が付かないが、何らかのヒントを提示している事は確かだった。
来ヶ谷唯湖を含めた例の四人が、同じ写真を所有していたのだ。
多分、それぞれが最も大切に保管できる場所、見栄えの良い最良の場所を選ぶように、あるものは仕舞われ、あるものは飾られていた。
何かの記念なのか、10人の男女が和気藹々と写っている。裏には『リトルバスターズ』と記載され、部活か何かのメンバーで
あることは容易に想像できた。
写真には私も映っていた。
巨漢の男と、いかにも清楚な印象の女性に上下を挟まれる形で、可愛らしく顔だけを覗かせて微笑んでいる。
まともな写真はこの世界ではそれ一枚きり。アルバムを時には見かけることもあったが、収められた写真のすべてが真っ白の紙切れと
化していた。何故かは分からないが、『何か』がこの写真にある―――ということを如実に物語っている。
彼らがどんな連中なのかはこの写真だけでは察することができないが、少なくとも私は幸せだったのだろう。
こんな表情で笑い合える友人が居たのかと思うと、我が事ながら羨ましいと今の自分を省みて、つくづく思い知らされる。
一日の終わりになると、私は毛布に包まりながら、来ヶ谷の寮にあるその写真を眺めては物思いに耽るようになっていた。
どれかは分からないが、多分この中に来ヶ谷唯湖も居るはずだった。
それはつまり、来ヶ谷唯湖と私は面識があったということになる。
私達は、一体どんな話をしたのだろう・・・?
* * * * * * * * * *
何日かが経過した。
昨日、女子寮を一通り終えることができた私は、その日ようやく男子寮に手を付けていた。
座席表の男女を調べる程度なら二、三日で事足りるだろうと当初は楽観していたが、物事には常に山あり谷ありだと、
私は改めて思い知らされる。
全員が地上階であれば苦労などしないのだが、それが上階となると話は別だ。基本的に鍵の掛かった寮部屋への侵入は、
ベランダをつたって二階、三階へよじ登るという行程が必要となる。右手の傷が癒えてない私にとって、この作業はかなり堪えた。
当然、正攻法で正面突破を試みたこともあったが、力任せの破壊や、針金を曲げての鍵の開錠など、体力と時間の浪費だと早々に
悟って以来、専ら壁登りが主流である。
寮部屋がカラッポであれば一瞥して戻れば良いだけの話だが、部屋の内装が保存されていた場合、一通り調べるという作業が
これに加算される。このときほど人の所有する物品の多さに嫌気がさすことはない。一部屋だけで長いときでは半日以上を費やすのだから、
調査は女子寮だけで相当の日数を消費していた。
今回の男子寮の探索で、調べていた生徒が初回から三階であると知ったときの私の気分が如何ほどであったかは推して知るべし―――。
後に回そうかとも思ったが、どうせ、いつかはやらなければならないノルマである。やるなら早めの方がいいと覚悟を決めて、
三階に住居を構える他の二名の部屋も、まとめて片付けたのが数分前のことだ。
先日失敬した水筒から、水が咽喉を伝うのも構わずごくごくと飲み干して、私は息を吐く。作業時には当たり前となって久しい
ジャージの袖で汗を拭うと、大した収穫もなく無駄骨に終わったことを、勤めて忘れてしまおうと次の作業に取り掛かった。
手際は慣れたものだ。傍に置いたバッグから寮の玄関口に張られていた部屋割り名簿と、教室にあった座席表を見比べては、
先ほどの部屋の留意点を書き込んでいく。
その姿は一介の女学生とは思えないほど凛々しいけれど、肌に載った疲労の色は隠しようがない。
孤島に一人だけ取り残された人間がはじめに飢えるのは、人との触れ合いだといわれている。寮部屋を探索する目的が、
その意味合いを変化させつつあるのもそこに原因があるのだろう。例の教室と、生徒たちの関連を解き明かすことよりも、
誰か他に人が居ないかを主眼に寮部屋を放浪している自分に気付いたのは、つい最近のことだ。
記憶喪失による精神的な不安と、「私は誰であるか」という強迫観念。
閉塞した世界と支えのない孤独感が、その気持ちを更に助長していたのだろうが、焦燥は強くなるというのに得られる成果は微々たるものだ。
ベランダをつたって上り下りする私の寮の探索と比べ、日常そのものは平坦で起伏がない。同じ日を何度も繰り返しているような、
奇妙な既知感に囚われてしまう。
そのためか、私がこんな目に合って、いったい幾日経過したのか・・・実を言うと、もうほとんど憶えていない。
降り注ぐ光のカケラは止む事を知らず、同じ風景と、同じ日常の繰り返しに、当の昔に私の心根は折れていたのかもしれない。
感情の限り叫んで、人を求めたこともあった。
「何でこんな目に・・・」と、一日中来ヶ谷唯湖の部屋から出なかったこともある。
私はもう知っている。ここには本当に、私一人しかいないという事を。
けれども、人を探さずにはいられない。暇を見つけては校舎の中も探してはいたが、確率的に誰かが居るとしたら寮部屋以外に
考えられなかった。
不毛と知っていながら、こんなことを続けている私は馬鹿なのだろうか。
それとも、どこかで狂ってしまったのだろうか。
窓を壊しても、部屋をめちゃめちゃに荒らしても、何事もなかったかように翌日にはすべてが元に戻っている事象を目撃してからと
いうもの、どこかで私の心のバランスは崩れ始めていた。
負担ばかりかけていた左腕は小刻みに震えていた。
それが伝染して、震えが身体を覆っていく。
誰でも良い。
ただ・・・誰かと逢って話しをしたかった。
バラバラに壊れそうな部品を繋ぎ止めている私の糸は、今にも切れてしまいそうだ。
それでも平静を装い、次の目標となる男子生徒の部屋を探していたところ、ある名前で目が止まる。
棗恭介・皆川早瀬 312号室
どこかで見たことのある名前だった。
私は最近の記憶を掘り起こそうと、感傷的になっていた気持ちを切り替える。
棗恭介・・・・。棗―――そう、棗鈴だ。
珍しい苗字からも、棗鈴と血が繋がっていると推測するのもあながち的外れではあるまい。調べてみても損はないと判断した私は、
とりあえずの目標を見つけることができて、ほんの少しだけいつもの平静さを取り戻す。
こういう収穫のあるときはいい。思考を循環させている間だけ、嫌なことから目を背けていられるから。
それにしても、例の教室の生徒にしか目が廻っていなかった自分が憎らしかった。
部屋番号からして三階だろう。軽く眩暈を覚えるが、そこはグッと堪えて名簿をバッグに仕舞い、小脇に抱えると、一応、
部屋のドアが開いていないかを調べに階段を上って三階へ向かう。
一度として開錠された状態の寮部屋というものを拝んだ事はないのだが、ベランダをよじ登るという重労働を回避する可能性が少しでも
あるのだ。この階段を上る程度の労力で済むのなら、確認してみる価値はある。
疲弊した身体に鞭打ちながら、私は一段、また一段と足を運ぶ。
それにしても、男子寮の名簿は見ていたのだが・・・棗恭介を見過ごしていたことが、どこか腑に落ちなかった。まぁ、棗鈴の
『家宅捜査』を行うまでは、あまり気にも留めていなかった苗字なのだから、見過ごしていたのも当然といえば当然なのかもしれないが・・・・。
例の写真には確かに兄妹らしい二人の姿が写っていたと思う。いかにもやんちゃそうな男と、どこか困った表情のポニーテールの少女。
棗鈴と棗恭介があの二人だとするなら、私と能美クドリャフカの合わせた四人が、あの写真の中で顔と名前が一致したことになる。
女生徒の来ヶ谷唯湖、神北小毬、西園美魚で女子の数は合うから、残った男子生徒3人を見つけることが今後の課題であろう。
これがすべて終わった先にある予感を、私は勤めて見ないようにしていた。これだけの時間と労力を費やしていながら、得られたものは
友人と思われる9人の存在を映した写真一枚きり。すべてが徒労に終わるであろうことをどこかで悟っていても、止めることなど私に
できるはずもない。
そこで足を留めてしまったら、私は『現実』を見つめなければいけなくなる。
過酷な現実を目の前にすれば、私の心はきっと死んでしまう。
だから私は、あの写真に依存する。
一日の終わりになると、あの中の生徒達との日常を空想しては、現実から飛翔して、もう二度とこの世界へ舞い降りてこないようにと
切に願って布団を被る。漂流したこの世界の方が間違いで、きっと夢か何なのだと自分に言い聞かせて・・・・。
どんなに強くあろうとしたって、私はちっぽけな一人の少女でしかない。力が強かろうが、どんなに賢かろうが、ひとりきりの自分を
満たす糧にはなりはしない。
こんな現実と今こうして付き合っているのだ。
少しくらい夢を見たっていいじゃないか・・・
舞い落ちる光の粒子は、とうとう寮の内部にも浸水していた。
どこから落ちてくるのか、ひらひら、ひらひらと私の目先を過ぎっては、小さな夢を灯しては消えていく。
空ろに沈む私の瞳は、やがてカケラの残骸に吸い寄せられる。
リトルバスターズの面子と、私の間にあった関係はどのようなものだったのだろうかと想いを馳せていると、うつらうつらと舟を漕ぐように、
気付けば私の意識はどこか遠くに流されていた。
私を苛めていた孤独と疲労が、とうとうピークに達してしまったのかもしれない。「こうであったら良いな」という過去を妄想しては、
現実から目を背けようとする何かが、私の『何か』を断ち切ろうと首に手をかけていた。
私が笑っている夢
私がささやかな恋している夢
私が多くの仲間たちに囲まれて、日常の学校生活を過ごす夢
とても甘くて、魅惑的な夢だ。いつまでも続けばいい。あの写真の仲間達に囲まれて、どこまでもどこまでも、楽しく平穏な世界を
ぐるぐると、ぐるぐると・・・・・・・・。
死ぬまで妄想の世界で生き続けれると言うのなら、それは確かに幸せなことなのかもしれない。
ふうっと訪れる陶酔に身を委ね、静かに闇に落ちそうになる私の背中を、誰かがそっと抱きしめたような気がした。
―――そんな世界、僕は認めない・・・・!!―――
誰だったろう?
以前誰かに言われた言葉が木霊した。
華奢な体つきをしているくせに、人一倍健気で、誰よりも優しくて、強い人。
だから私は・・・。
私は・・・・・・・
「・・・どうしたのだろう・・・?」
数日に渡る強行軍で、肉体的にも精神的にも限界に達していたのだろう。階段の途中で崩れるように倒れていた私は、
夢心地の頭を振って起き上がる。
何かを思い出しかけていたような気がしたが、それももう、夢と共に曖昧なものとなっていた。
無理な体勢で倒れていた為か、節々が痛い。散らばった所持品を拾い集め、廊下の窓から外を見回すと、いつの間にか三階まで
来ていたようだ。夢遊病者じみたあんな状態で、よくここまで来たものだと呆れてしまう。
ふと横を見れば314号室は目と鼻の先だ。
この部屋にもやはりあの写真があるのだろうか・・・・。
錠が掛かっていることを覚悟して軽くノブをひねると、拍子抜けるほど簡単にドアが開く。息を呑み、私はゆっくりと中を窺った。
光の届かない深海のように、深い闇が部屋を支配していた。
目を凝らすと、うっすらとだが二段ベッドらしき輪郭や、勉強机、平積みされた数冊の雑誌が識別できる例外的な空間だ。
どうやら棗鈴の血縁者という仮定もあながち間違いではなさそうだ。
例外者の中では私が見つけた初の異性でもある。新たな発見があるかもしれないと期待に胸を膨らませるが、こう暗くては
作業に差し支えが出る。
手始めに遮光カーテンをなんとかしないと・・・
部屋に足を踏み入れた私のすぐ後ろで突如ドアが閉まった。
慌ててドアを振り返るが暗くて何も見えない。おおよその見当で延ばした私の腕は虚空を薙いだ。
「・・・・・来ヶ谷・・・か?・・・どうやってここに?」
男の声が響いた。
人間の声だ。
記憶を失った私にとっては、“生まれて初めて聞く”他人の声。
一人じゃないことの嬉しさが全身を駆け巡るが、男の言葉を反芻していくうちに、私はゆっくりとだが醒めていく感覚を憶えた。
繋がった先の『ソレ』と自分を照らし合わせて、何かが鮮明になっていく。記憶の奔流と、混濁した感情。
頭の中が割れそうに痛むのを堪えて、確定した私という個体の正式名称を口にする。
「私が・・・・・・・・・・来ヶ谷・・・唯湖なのか・・・・・・・・・」
じゃあ、例の教室で無意識に自分の机に座ったことは一つの必然だったのか?
鍵と携帯が放置されていたのは、記憶喪失前の私が置いていただけ?
じゃあ、あの例外的な空間は・・・・
嵌り続けるピースの数は膨大に膨れ上がる。
圧倒的な物量に堪えきれず膝を突き、それでも私は男の顔を見ようと闇に目を凝らす。
「お前は誰だ・・・・・棗恭介か?」
質問の意味を巧く把握できなかったのだろう。
しばらくの沈黙が終わると、男は意外そうな声を上げた。
「・・・・おいおい、まさか完全に記憶をなくしているのか? そんな状態でどうやってあの世界を持続させて―――いや、そうか・・・。
それで俺の部屋に繋がったというわけか。記憶喪失にでもならなければ、お前が好き好んで俺の部屋にくるはずもないし・・・・
整合性は確かに取れるが・・・・」
「・・・・・・何が言いたい!? なにを言っている!?」
一人納得する男に苛立ちを隠せない私は、奥へと進む。
部屋の隅に浮かぶシルエットが、もぞりと動いた。
「来ヶ谷。お前の世界はもう終わりを迎えている。そこにあるのはただの『残骸』だ。“こっち”と繋がったのは、綻びの隙間を
巧く掻い潜れたからだろうという仮定しか出来ないが・・・・恐らく、お前の世界が完全に終わりを迎える前兆だろう。
・・・今のお前に話しても理解できないだろうが、お前の願いにはそもそも無理があったんだよ。『永遠』を願ったところで
破綻が生じる事は分かっていたはずなのに・・・・どうしてお前はその世界を願ってしまったんだ・・・」
分からない。
彼が何を言わんとしているのか私には理解できない。
「他に、願うべきものがあっ・・・た・・・ろ・・・。両親・・・関係・・・の修・・・・・・・・・・の・・・・に・・・」
「待ってくれ! 聞こえない! この世界はまやかしなのか? どうすればここから出られる!?」
男の声が遠い。物理的距離は3mもないというのに、歩み寄る私と男との距離はいくら経っても縮まらなかった。
あと、少し・・・あと少しがもどかしい。
「・・・・な・・・おえ・・・・き・・・。・・・わ・・・す・・・・れ・・・」
手の先が男に届いたのは直後のことだ。布地と思し手触りを頼りに私は一気に男を引き寄せる。
聞きたい事は山ほどある。そして男はそれを答えれるだけの知識を持ち合わせているらしかった。まずは顔だ。
写真の男なら、リトルバスターズについても聞けるだろうしこちらとしては好都合だ。
私はカーテンを力任せに引き毟る。レールごと盛大に剥がれて、外光が闇を駆逐する。
そうして目の前にあったのは、襤褸と化した唯の布切れだ。
男はおろか、部屋の中に確かにあったはずの二段ベッドもなければ、男のもとへ向かう最中によけたはずの、ゴミや雑誌の山は
陰も形もなくなっている。
狐に抓まれた面持ちの私は、辺りを見回して更に呆然とする。
314号室だった部屋は廃墟と化していた。
天上や側壁は失われ、吹きさらしの空からは、光の飛礫が舞い込んでいた。
いや、314号室だけじゃない。隣も、その隣も・・・・男子寮はおろか、数十メートル先にある校舎、女子寮、体育館。
何から何までが廃墟一歩手前の零落ぶりを晒している。
この世界の終わりの前兆―――
男は確かにそういっていた。
それが・・・・これか?
漂流していた学校の敷地はとうとう闇に飲まれ、グランドの半分近くが削れてなくなっている。侵食速度は以前と比べ物にならないほど
速く、数時間もすれば、すべてがあの闇に覆われるだろう。ここでオメオメしてたら私も崩壊に巻き込まれる。
314号室前に転がっていたバッグを抱えて、私は寮部屋を後にした。
とにかくこの世界から抜け出す方法を探さなければいけない。
最後に男はなんと言った?
なお・・え・・・・・直枝・・・・・
どこかでそんな名前を見かけたような気がして、座席表と、寮の部屋割り表を私は取り出した。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なんだ・・・・・・これは・・・・?」
プリンターで印刷された紙面の文字は、数十年の時を経たように擦れていた。名前を確認しようにも、うっすらと見えるのは
罫線くらいのもの。私の座席の場所がどうにか判断できる程度の解像度で、誰かの名前を特定するなどできるはずもない。
ついさっきまで普通の紙であったものが、どうやったらこうまで劣化するというのだ。
せっかく、何かが見えはじめたというのに・・・・!
私は力任せに地面に叩きつける。その一撃が紙書類の寿命を終わらせた。
チリ屑と化した紙吹雪は上空を舞い、それは突然、光の粒子となって虚空へと還っていく。
唖然とする光景を目の当たりにして、私はようやく光のカケラの正体に気付くことができた。地面も、草木も、建物に至るまで・・・・。
降っていたと思っていた光の粒子は、この世界を構築していた物質そのものなのか。
作り物の世界。その残骸の中で彷徨っていたのがこの私・・・来ヶ谷唯湖だったと言うわけだ。じゃあ私も誰かに創造にされた
作り物なのだろうか?
可能な範囲で自分の身体を調べてみるが、光の粒子が私から漏れ出す気配はない。少しだけ安堵するが、状況は何も変わってなどいない。
何か・・・何かできることはないかと思考を巡らせる。
直枝という人物の手がかりは何もないといっていいが、ある程度の推測は可能だ。リトルバスターズのメンバーの一人とするならば、
あの教室のどこかにそいつの机があるかもしれない。運がよければ所持品を見つけ・・・・そして更に運がよければそこから脱出する
手段―――。
常識的に考えて、そんなご都合的な可能性はゼロだとは分かっている。
けれど、動かなければここで屍を曝すだけだと走り出す。
例の教室はまだ健在だった。隣接する教室が既に朽ちているというのに、ここだけ日常の息吹を保管している。
区切られた境界を潜るように、私は教室の中へと舞い戻っていた。
窓の外から見える世界の終わりを告げる光は、その数を何千、何万と増やして一面を真っ白に塗り潰している。
チラホラとその光に混じって、遠い彼方の風景が二重写しに霞んでいた。
季節は初夏だろうか。
暑い日ざしが差し込み、木々がその緑を深めている。
白く塗られたキャンパスの先には、私の見知らぬ世界があった。
この世界はもう崩れ始めているのだ。このままここで息を潜めていれば、もと居た場所へと帰ることができるのかもしれないという
誘惑が過ぎるが、私は大きく首を振る。
違う。
まだ帰れない。帰ってはいけないと本能が警告していた。
私は何かを忘れている。この世界に何かを置き忘れたままだ。
戻った瞬間それは消えてしまう。
それではダメ。
それではこの世界を願った・・・・・・・意味が・・・・
今・・・私は何を口走った?
あの男と出会ったことで、何かが・・・・忘れていた記憶の断片が、ここに来て私の中に生まれつつあるのだろうか。
かつては他人だと思っていた来ヶ谷唯湖。その席に私は座り、必死に何かを思い出そうと努力する。そう、私は何かを願ったのだ。
全てをかなぐり捨ててそれだけを願った。それだけあれば他はもういらないとさえ祈った自分の気持ち・・・・。
あったはずなのに・・・・
痛いくらいに拳を握る。
思い出せないことが自分の罪であるかのように髪をぐしゃぐしゃにすると、声にならない絶叫を上げて私は机を蹴り飛ばした。
愚か過ぎる。
願いをした本人が全てを忘れているというのに、その願いだけが一人歩きをして、こんな世界を未だに残し続けているという事実が。
この世界は、私に何かを教えようとしている。そうでなければ、こんなにも無残になった状態で存続し続ける意味がない。
それとも無意識に、私という主体がこの世界に今に至るまで何かを願い続けているのかどちらだろう。
ダメだ・・・考えても分からない。
力なくうな垂れる私の顔はとうとう下を向いた。
携帯電話があった。
来ヶ谷唯湖の・・・私の携帯電話が、机が蹴り飛ばされた拍子に転がっていた。
全身に鳥肌が立つ。
藁をも掴むように私はそれを手に取った。
そうだ。あったはずだ。メールで、私は誰かに宛てて恋文を送り続けていた。
確信する。私が思い出すべき事はそれ以外にありえない、と。
私はゆっくりとメール履歴のボタンを押した。
受信メールはありません
たった一文の報告に、私の思考は停止した。
そして、ただ可笑しくて笑い出す。
そんな馬鹿な。あるはずがない、何かの間違いだともう一度、履歴ボタンを押す。
受信メールはありません
・・・・・・ありえない。
ありえない。ありえない。ありえない。
消した記憶はない。机から落ちた程度でメモリが飛ぶとも思えない。
送信メールの履歴も調べてみるが、こちらもどういうわけか『送信メールはありません』という無機質な文面が羅列されている。
電話の着信履歴、リダイヤル、友人のメールアドレスや電話番号の全てが初期化されていた。
購入したての市販品のようなものに成り下がってしまったそれを取り落とし、ただ無言で私は首を振る。最後の希望が枯れ落ちてしまった。
それを合図に、守られていた教室、机、私品の多くから・・・・光が洪水となってあふれ出す。
手遅れだったのだというには、あまりにも『それ』は近くを通り過ぎていた。
私が・・・来ヶ谷唯湖が思い出すべきだった何かを連れて、世界は徐々に白に埋もれていく。
こんなことで終わるのか?
この程度で私は何かを失ってしまうのか?
いやだ、いやだ・・・・!
気力を揺り起こして立ち上がると、もう不要とは分かっていたが、何かを閉じ込めていた携帯を、“遺品”を手に取るように
大事に抱えて私は教室を抜けた。ドアを抜けると同時に、他の教室と同様の姿に聖域は崩れ落ち、置いてあった私のバッグも、
それの余波を受けて光となって消えた。
よろよろと立ち上がる私の手元に残ったのは携帯と、三つの鍵束。
記憶を保持していた頃の、来ヶ谷唯湖の遺留品とも言うべきそれが、私に与えられた唯一の活路だった。
鍵の一つは寮の部屋としても、残りの二つは私に何を示唆しているのだろう。
一つは寮の鍵と似た形状で、残りの一つは3cmほどの長さのチャチな造りをしている。
使用場所は皆目見当も付かないが、何かの役に立つかもしれない。ポケットに仕舞うと、渡り廊下を抜けて、私は対向側の校舎へと
移動する。闇の侵食は、程なく向かいの校舎を飲み込んだ。気付けば寮側に立っていたこの校舎しか残っていない。
廃校同然のここが、最後の砦というわけだ。
だが、まだ全てが終わったわけじゃないと私は自らを鼓舞する。
崩壊が始まって、全てのものが崩れ落ちているという事は、逆に考えればチャンスでもある。
寮や例の教室のある校舎は一通りの調査を行ったが、寮側にある校舎は優先順位が低かったこともあり、それほど調べたわけではないのだ。
仮にあの教室のように、例外的な空間が存在するのであれば、今のこの状況なら、記憶を喪失した私にでも重要性が視覚的に
把握することができる。要は崩壊していない場所や物を探せばいい。
見つけるのだ。この崩壊の跋扈した世界で、来ヶ谷唯湖の想いを保持した『何か』を。
今の今になって、ようやく私は疑問の氷解音を聞いていた。
答えは単純だったのだ。
この世界の影響を受けずに残存していた例外的な空間や物は、私と繋がっていた。
リトルバスターズの写真
その中で笑う友人達の部屋
私が通っていた教室
来ヶ谷唯湖である私の部屋
全部、全部意味があった。
無意味なものなんて一つもなかったのだ。
ガラクタと吐き捨てた、あの教室にあった物品も突き詰めていれば、きっと何かの役に立ったかもしれないのに。
一階の廊下をひた走っていた私は『それ』を見つけていた。
周囲と比較して充分綺麗なドア。影響を受けていない証拠だ。
「放送室」というネームが貼られているが、果たしてこんな場所に何かあるのだろうかと首を傾げてしまう。しかも、当然のように
施錠されたドアはビクともせず、崩壊を起していない代わりに、私をも締め出して盤石の鉄壁を誇っていた。
裏から何とかならないかと外に向かおうとしたが、玄関口で生じた鈍い音が、私の勇み足を押し留める。ぐらりと校舎が揺れたのは
その直後だ。
玄関左手の校舎下の地表がとうとう闇に食われたのだ。寄りかかる土台を失くした校舎は自重に負けて半壊した。
体勢を低くしていた私には幸いにも大した怪我はなかったが、振動でもんどりを打った拍子に足首を挫いていた。
震災の第一波が収まるのを確認して、ひょこひょこと足を引き摺りながら窓に向かうと、私は身を乗り出して外を窺う。
あたり一面は闇の海と化していた。
空には崩れ落ちた天蓋がぽっかりと開いている。それはもう空というよりも、きらきらと光る豪華なシャンデリアを叩き壊した
瞬間の映像だ。ぶちまけられた光の粒が闇の黒に映えて、思わず見惚れてしまうそうだ。
天も地も周囲の建造物も根こそぎ消滅している。
食べ残しはここだけというわけだ。
あまり考える時間もないというのに、この堅牢なドアを攻略する方法で、ろくな案が浮かばない。寮のベランダから侵入というような
アクロバットな小技はやりたくても、右手は痛むし、足首は痛い慢心創痍状態。
移動も無理、力技も無理ときてはさすがの私も手の打ちようがない。
「もうここまでかな・・・・」
ニヒルなタフガイなら、ここでタバコの一つでも燻らせるのだろうが、生憎と私の手元に、そんな物は・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
サイドポケットに手をやると金属特有の硬質な手触りがあった。
取り出してみると鍵の束。
一つは寮の鍵。
そして一つは同系の鍵。
まさかな、とは思いつつも、その鍵を錠に差し込むと見事に嵌り込む。
そのまま半時計方向に回すとカチリ―――という小気味いい音を立てて部屋は私を招きいれていた。
狭い部屋だ。
もともと放送だけを目的としているであろう部屋に、マイクやら面倒そうな設備がこれでもかと突っ込まれているのだから無理もない。
奥には電子ピアノらしきデカブツが鎮座しておりなかなかに壮観だ。
放送室に入ると同時、朝からずっと酷使し続けた身体はもう限界だった。倒れこむようにフローリングの床に身体を横たえると、
私はそのまま身動き一つ取れなくなる。
床の冷たさがほてった身体に心地いい。妙な達成感を憶えて、私はこの世界で初めて作り笑いじゃない、本当の微笑いを浮かべることが
できた。
ここが私の終着点。
そして、多分・・・記憶喪失以前の来ヶ谷唯湖が一番の想いを込めた場所。
記憶喪失以前の私がここに何を感じ、何を経験して、何をしていたのかは分からない。
分からないけれど、それはきっととても大切なことだったんだろう。
闇と光のカケラに飲みこまれもせずに、最後までここが残ったのも偶然じゃない。
“ここを中心にして作られた世界”だからこそ、最後に残ったのがここだったというだけなのだと思う。
それが分かっただけでも、私は満足だった。
胸に酸素を充填すると、やがて私は大きく息をつく。
一人の少女によって創られた世界は、とうとうその限界を迎えていた。
不完全で、不恰好だったカタチは歪み、『世界の中心』である放送室へと闇は進行する。
壁が光のカケラとなって消えていく。
床も、機材も、そして、私自身も・・・・
恐くはなかった。
徐々に埋没する足はその存在感を失い、やがて腿、腰、胸を覆い・・・
最後に私の顔はとぷりと沈んだ。
結局、直枝という人物だけがよく分からなかったなと、私は感慨深く呟いた。
男なのだろうとは薄々とは感じていたが、やはりそれが誰なのかを理解することができないまま、来ヶ谷唯湖である『私』が、
私ではなくなることが少しだけ心残りといえた。
混濁した意識の中で、私は奇妙な夢を見る。
私が誰かに恋をしているという夢。
それは叶わぬ恋であり、私自身も分かっている悲しい夢。
とても儚く悲しいけれど、分かっていても、やはり私は彼を好きになるしかなかったんだと諦めたように小さく頬笑う。
けれどそれは夢。
どんなに苦しくて、恋しくても、それは夢。
だから忘れてしまおう。
悲しかったことも嬉しかったことも、全部この夢に詰め込んで―――
あとがき
|ω・`)
うん、多分一番空気読めてない作品だと思います。
というわけでまずは一言言わせてください。
スンマセンでしたー!!!!!!orz
さて(ぉ
今回のSSは、ウチのブログの『二次創作考察小説』というSSの番外編的位置付けの作品だったりします。やれることなら来ヶ谷の
補完的な作品もやりたいなと思っていた自分にとって今回の来ヶ谷祭はまさに渡りに船ということで投稿させていただきましたm(_ _)m
基盤にあったのは来ヶ谷シナリオの終盤からラストへの件に至る間の補完を、自分なりに妄想して書いてみたいというだけの話
なんですけどね(笑
全て読んだ方は色々言いたいことがあるでしょうが、題にもあるようにこれはあくまでもこれはver.B。
初回プロットとして自分の頭の中にあったのは3つ。
三つとも途中までは共通なんですが、終盤からの展開が分岐する仕様となっております。
まず今回のバッドエンドルートのVer.B(バッド)
終盤で実は『私』が来ヶ谷唯湖じゃないという超展開をするVer.F(フェイク)
コイツに関してはまぁ、さすがにアレだよなぁと思ってプロット段階で破棄しましたが、もうひとつのバージョンは恐らく、
これが上がる頃には完成してウチのブログにうpられていると思われます。
来ヶ谷シナリオといったら二つのエンドが唯一あるヒロインですからね。
考察を書いたりと思い入れがあるので、このような実験をさせて頂きました。
OKしてくださった神主あんぱんさま
そして今回リトルバスターズの簡易メモで、マップを参照させていただいた神海さま。
挿絵を描いていただいたごすさまにこの場を借りて感謝をm(_ _)m